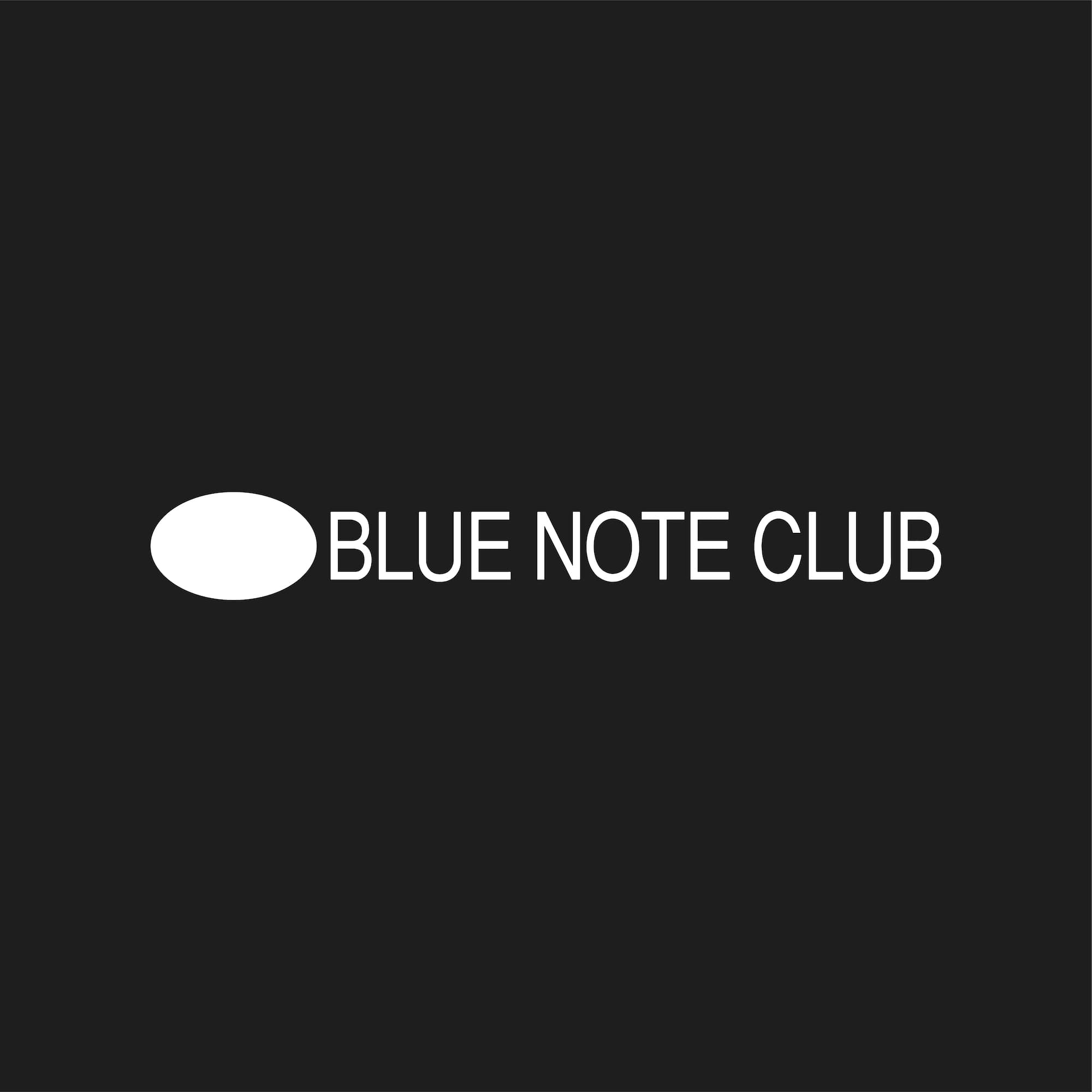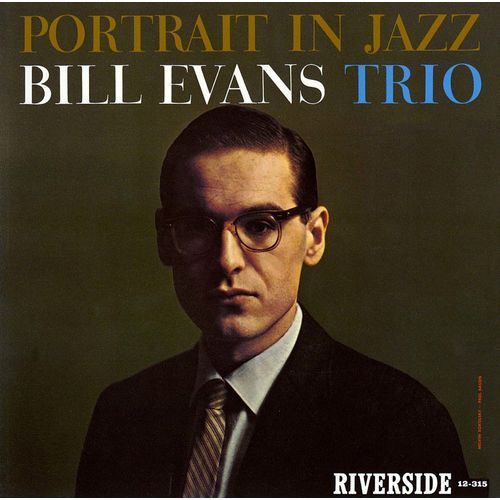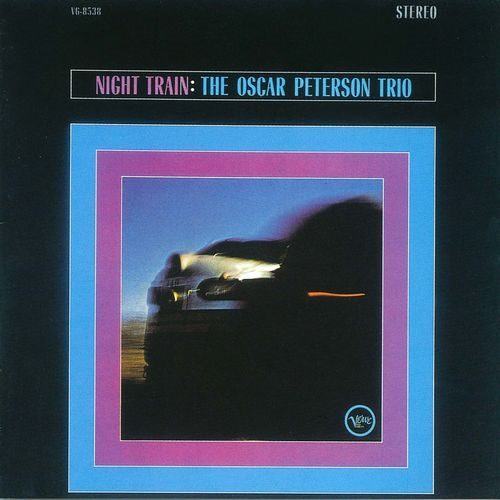クイズです。〇の中を埋めましょう。
●先日COVID-19で亡くなったプロデューサーのハル・ウィルナーはかつて、ウォズ・ノット・ウォズ(ドン・ウォズ参加)、ドナルド・フェイゲン、ドクター・ジョン等を迎えて、〇〇〇〇〇・〇〇〇へのトリビュート・アルバム『That’s the Way I Feel Now』を制作した。
●デイミアン・チャゼル監督の大ヒット映画『ラ・ラ・ランド』には、〇〇〇〇〇・〇〇〇の演奏する「荒城の月」が何度も挿入されている。
●『ダーティハリー』シリーズや『グラン・トリノ』などで知られる俳優/映画監督のクリント・イーストウッドは、〇〇〇〇〇・〇〇〇を題材にしたドキュメンタリー映画『ストレート・ノー・チェイサー』を制作したことがある。
●ロバート・グラスパーは映画『ブルーノート・レコード ジャズを超えて』の中で、〇〇〇〇〇・〇〇〇について「自分自身を持ち、ぐらつかない。思うに彼こそ最初のヒップホップ・ピアニストだ。ジャズにはない揺らめきがある」と語った。
●ヒップホップの大プロデューサーにしてジャッキー・マクリーンを敬愛するテラス・マーティンは「若いころ彼から学んだんだ。“自分自身であれ、隣りが何をしようが、どんな音を出そうが自分の証を演じ、立ち上がれ”とね」と〇〇〇〇〇・〇〇〇について述べている。
●小説家の村上春樹は2014年に『〇〇〇〇〇・〇〇〇のいた風景』を発表した。
●この8月に4K上映される伝説的ジャズ映画『真夏の夜のジャズ』の中で、〇〇〇〇〇・〇〇〇はウッドフレームのサングラスをかけて演奏している。ファッション・センスも実に独創的だった。
●ティグラン・ハマシアン、ジャズメイア・ホーン、ジョシュア・レッドマン、マーカス・ストリックランド、グレッチェン・パーラート、アンブローズ・アキンムシーレなどを輩出した世界最高権威のジャズ・コンテストは、2018年まで「〇〇〇〇〇・〇〇〇・インスティテュート・オブ・ジャズ」によって運営されていた。
●最新作『EYES』も圧倒的だったエクスペリメンタル・ソウル・バンド、WONKが所属するレーベルのエピストロフはブルーノート・レーベルと組んで発表した『Monk’s Playhouse』は〇〇〇〇〇・〇〇〇へのトリビュート作品。WONKはもちろん、常田大希(King Gnu、millennium parade)、MELRAWなど彼の音楽に影響を受けたミュージシャンやヒップホップDJが参加している。
●トリビュートといえば、マルチ・ミュージシャンでプロデューサーのティム・コンリーことマスト(MAST)が制作したアルバム『Thelonious Sphere Monk』も傑作だ。マカヤ・マクレイヴン、クリス・スピード、ブライアン・マーセラなどが参加。ブライアンはハサーン・イブン・アリ作品集もリリースしているが、このハサーンもまた、〇〇〇〇〇・〇〇〇同様、才能に富んだ作曲家であり、打楽器のようにピアノを弾く。
●ブルーノート、プレスティッジ、リヴァーサイドという、いわゆる“ハード・バップ三大レーベル”すべてにリーダー録音を残したのはアート・ブレイキー、ソニー・ロリンズ、ミルト・ジャクソン、〇〇〇〇〇・〇〇〇である。にもかかわらず〇〇〇〇〇・〇〇〇の音楽はハード・バップではない。
正解はもちろんセロニアス・モンクだ。そのくらい彼の音楽は現在につながっている。現代へ流れている。考えるほどにこれはすごいことだ。彼は1960年代に入ると作曲をほとんどやめ、70年代前半には演奏活動からも遠ざかって、長い隠遁生活のすえ82年に亡くなった。もう40年も前に生涯を閉じてしまった男が、こんなにも敬愛され、歓迎されたまま2020年の空気の中でもなお存在感を発揮しているのは奇跡であり胸のすくような快挙ではないか。
そしてこの夏、モンクの“新作”『パロ・アルト〜ザ・ロスト・コンサート』が発売されることになった。彼ほどの人気者になると非公式のライヴ音源もそれなりに出回っているのだが、いろいろ嗅ぎまわり、探し回っている僕でもこのセッションに出会うことはなかった。まさにお宝、完全未発表のテイク集だ。1968年10月27日の午後、カリフォルニア州パロ・アルトにあるハイスクールで行なわれた特別コンサートの記録。そういう催しがあったということはロビン・D.G.ケリー著『Thelonious Monk: The Life and Times of an American Original』に記されている通りだが(紙幅の都合か、邦訳『セロニアス・モンク 独創のジャズ物語』ではカットされてしまった)、こうして実際の音として楽しめる喜びは何ものにもかえがたい。
メンバーはセロニアス・モンク(ピアノ)、チャーリー・ラウズ(テナー・サックス)、ラリー・ゲイルズ(ベース)、ベン・ライリー(ドラムス)という、1964年上旬から変わらない顔ぶれ。つまりこの4人が活動を共にしてから5年目に突入していた。ラウズとモンクは59年から共演を続けているので、こちらは10年目だ。昭和育ちのジャズ・ファンならこの時期のモンクを“変わりばえしない”とか“いつまでチャーリー・ラウズを起用しているんだ”とか評したはずだが、68年のモンク・カルテットを捉えた記録は、実は非常に少ない。その理由についてはケリーが書いたライナーノーツに記されているが、ようするに体調が下降線をたどり、5月には発作を起こして入院、昏睡状態に陥る。当アルバムに捉えられているのは、復帰してカンを取り戻していた時期のモンクなのだ。それにしても、このコンサートが行なわれた1968年は多くのことがありすぎた。キング牧師やロバート・ケネディが暗殺され、ベトナム・ソンミ村の大虐殺が起こり、五月革命にプラハの春、メキシコ・オリンピック表彰式の“ブラック・パワー・サルート”等。音楽に目を転じるとマイルス・デイヴィスがスーツを脱いでエレクトリック楽器を導入、サイケデリックやファンクの嵐が吹き荒れてドアーズ、ジミ・ヘンドリックス、スライ&ザ・ファミリー・ストーン等が猛威をふるった。モンクはインタビューを嫌い、ライヴでもMCをしなかったので、当時の彼が何を思い、何を意識しあるいは無視したのかは謎だ。しかしこの10月27日もモンクたちは(おそらく)スーツにネクタイで登場し、1940年代に書いた、もう何百回もプレイしてきたであろう自作を中心に、まるで正義がそこにしかないなのように4ビート基調のパフォーマンスを繰り広げた。当時、管楽器用に“マルチヴァイダー”“ヴァリトーン”、ウッド・ベース用に“トビー”という電化装置が開発されていて、それを使うジャズメンもいたのだが、モンク・カルテットはひたすらアコースティックな音を出す。もっともそこにはある種の変化もみられ、ラウズは61年から63年くらいのセッションで頻発する指癖フレーズ(文字にすると“タティラッタラ”という感じ)をほぼ完全に取り去って、ダブル・タイムによる吹奏も思いのまま。ゲイルズがここまでアルコ(弓弾き)を多用したソロを聴かせるのも珍しい。
さらに興味深いのはライヴがバラード「ルビー・マイ・ディア」で始まっていること、ソロ・ピアノ曲を2つ含んでいることだ。モンクのライヴはだいたい速めのテンポで始まり、途中1曲ソロ・ピアノをはさみ、バンド・テーマ「エピストロフィー」で終わり、アンコールはない。しかしここでは「エピストロフィー」の後、「アイ・ラヴ・ユー・スウィートハート・オブ・オール・マイ・ドリームス」がフェード・インする。カルテットの後、鳴りやまない拍手にモンクが答え、ピアノに戻っていきなり演奏しだしたのではないか。驚いた録音係が、切っていたマシンのスイッチを大急ぎで再び入れた・・・それがこのフェード・インの真相なのではないかと僕はひとり想像している。
父セロニアスの権利を管理する息子T.S.モンクは、この音源に関して「一聴して、オヤジが機嫌のいいときの演奏だと分かった」と語ったという。確かにパロ・アルトでのモンクは相当、乗っている。いつどこの記録とはいわないが、このカルテットには、ただむなしく時間だけが過ぎていくようなパフォーマンスもある。だが本作での彼らはモンクを筆頭にとことん生き生きしていて、それぞれのパフォーマンスに暖かな血を通わせている。発掘・リリースの意義がありすぎるほどあるありがたき一枚、それが『パロ・アルト〜ザ・ロスト・コンサート』なのだ。
■作品詳細
セロニアス・モンク『パロ・アルト ~ザ・ロスト・コンサート』
日本盤リリース日:2020年10月7日
品番:UCCI-1048
価格;\2,860(税込み)
https://TheloniousMonk.lnk.to/PaloAlto
■収録曲
01. ルビー・マイ・ディア / Ruby, My Dear (6:59)
02. ウェル・ユー・ニードント / Well, You Needn’t (13:16)
03. ドント・ブレイム・ミー / Don’t Blame Me (6:36)
04. ブルー・モンク / Blue Monk (14:02)
05. エピストロフィー / Epistrophy(4:25)
06. アイ・ラヴ・ユー・スウィートハート・オブ・オール・マイ・ドリームス / I Love You Sweetheart of All My Dreams (2:02)
ユニバーサル ミュージック
https://www.universal-music.co.jp/thelonious-monk/