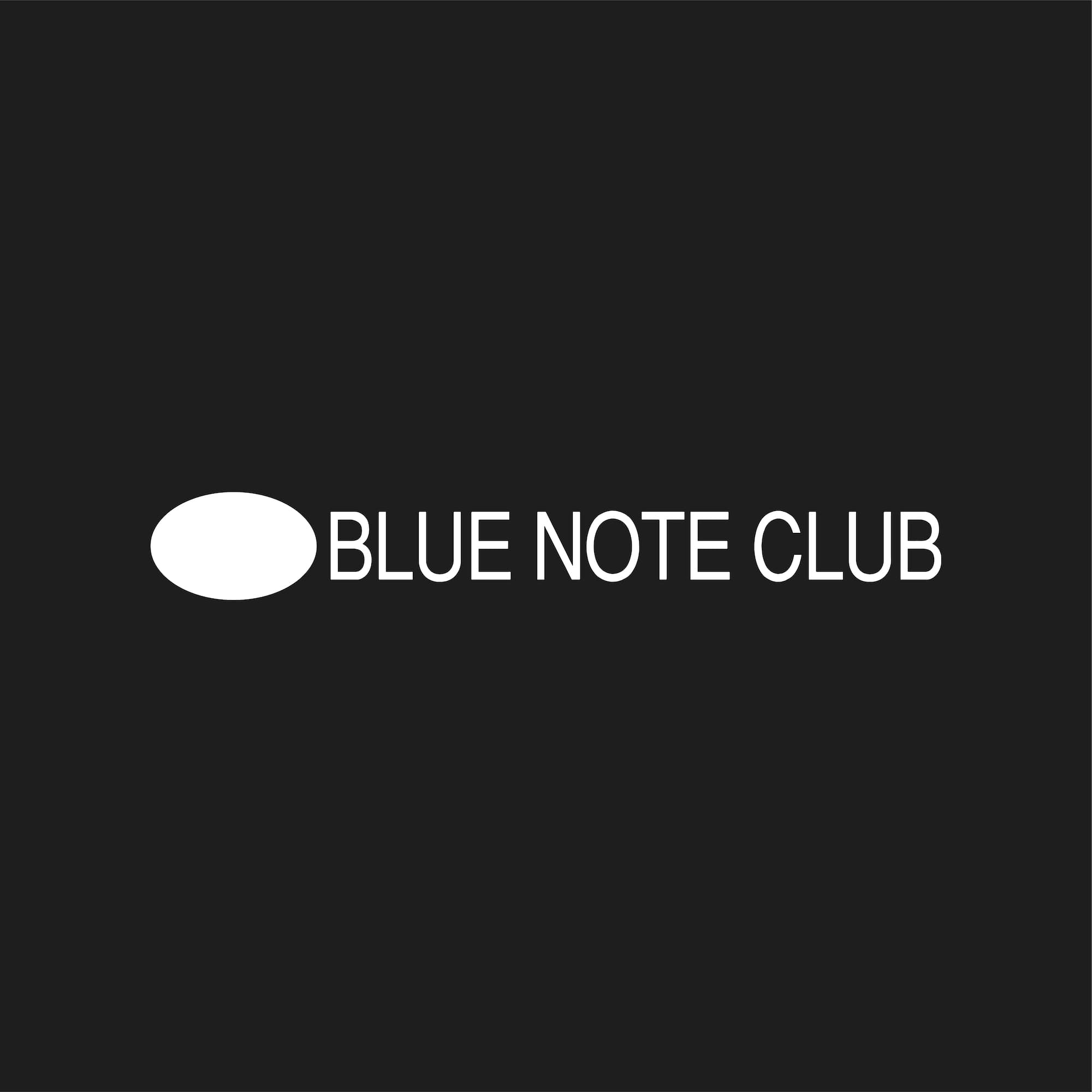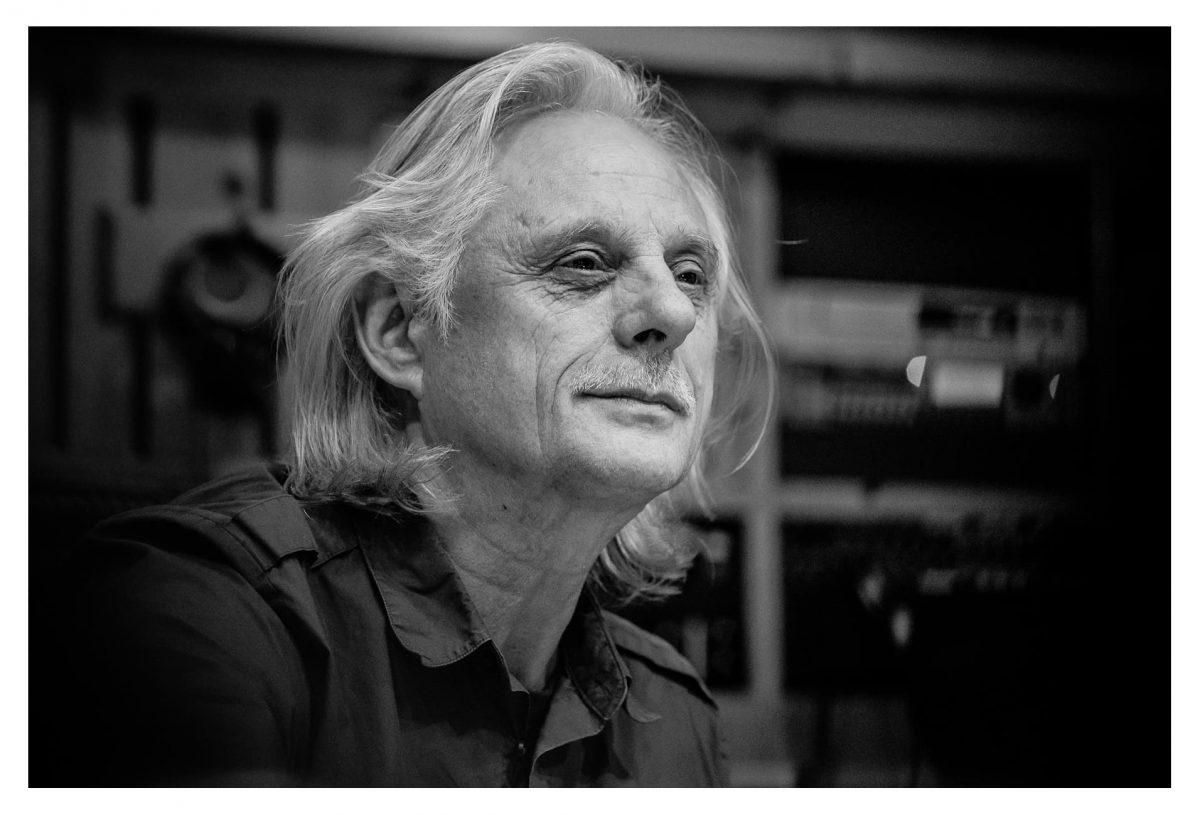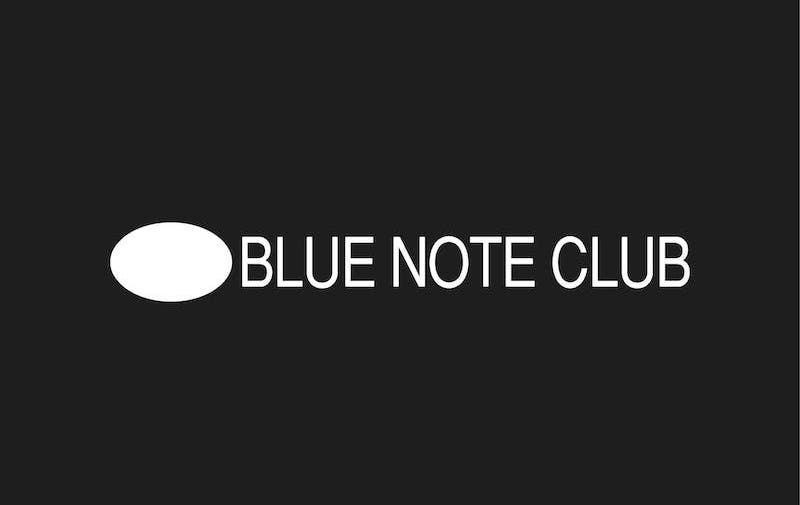毎年恒例、BLUE NOTE CLUB執筆陣による今年愛聴したジャズ・アルバム3枚をご紹介します。
2023年も名門ブルーノートがすごすぎた。ジョシュア・レッドマン、ケンドリック・スコット、ジュリアン・ラージ、アルテミスといった現代ジャズの中心人物から、デイヴ・マクマレイ、ジョー・チェンバースのベテラン勢、クリス・ボッティのような意外な契約もあれば、ラテンジャズのハロルド・ロペス・ヌッサもいた。
そして、ハイブリッド系だとミシェル・ンデゲオチェロやコーシャス・クレイといった異才がジャズ・シーンのトッププレイヤーとコラボしたことで生まれた傑作もあったし、UKに目を移せばロンドン・ジャズの拠点を舞台にした企画盤『Transmissions from Total Refreshment Centre』もあった。2023年のジャズにこれだけ大きな貢献をしたレーベルは他にないだろう。
ロバート・グラスパーやホセ・ジェイムズの成功への道筋をつけたことなどを見ても明らかなように随分前からブルーノートがジャズ・シーンを支えているのは間違いないが、そういったハイブリッドなサウンドだけでなく、いわゆる「ジャズ」のリリースに関しても抜きに出ているのが近年のブルーノートだ。ジョエル・ロスやイマニュエル・ウィルキンス、ジェイムズ・フランシーズら若手のリリースが話題になっているが、近年はジャズ・シーンの中堅、ベテランを積極的にリリースしている。今年だけでも前述のジョシュア・レッドマン、ケンドリック・スコット、ジュリアン・ラージ、アルテミスに加え、アルトゥール・オファリル、ジョナサン・ブレイク、ウォルター・スミス3世の良作がリリースされていた。
今や1500番台や4000番台、BNLAといった名作群をリリースしていた時期と比べても見劣りがしないカタログが揃っている。これはシンプルにとんでもないことだと思う。
アルトゥール・オファリル『Legacies』

今年のブルーノートのリリースで個人的に最も聴きこんだのがアルトゥーロ・オファリル。アルトゥーロはアメリカのラテンジャズの黎明期の最重要人物として知られるチコ・オファリルの息子。そして、上原ひろみのHiromi's Sonicwonderのレギュラー・トランぺッターのアダム・オファリルの父。偉大なオファリル家のひとりということになる。
基本的にビッグバンドの作編曲が活動の中心にあって、キューバの要素を盛り込んだラテンジャズビッグバンドの最重要人物として知られている彼がブルーノートからの2作目としてリリースしたのは作編曲家ではなく、ピアニストとしての録音。クラシック出自でジャズに傾倒し、そのうえでラテンジャズの流儀をもマスターした名手がその資質をまっすぐに表現した。クラシックにフリージャズ、ビバップが同時に聴こえてくるパワフルかつエモーショナルなピアノがたまらない。重量感のあるピアノを軸にしたゴリっとした異物感があるスタイルは今ではなかなか聴かれないもの。その中に少しだけラテンの要素が入ってくる塩梅も素晴らしいです。
ジョナサン・ブレイク『Passage』

今や世界最高峰のジャズドラマーの地位を確立しているジョナサン・ブレイクもブルーノート移籍後、好調を維持している。本作はイマニュエル・ウィルキンス、ジョエル・ロスの若手に、キューバ出身の奇才ダヴィ・ヴィレイジェス、名ベーシストのデズロン・ダグラスとのクインテット。
ジョナサンと言えば、コンテンポラリー・ジャズど真ん中のイメージもあるが、本作はジャケットのアートワークの雰囲気からもわかるようなどこかノスタルジックな曲もあり、モダンジャズ的なムードもあるのが興味深い。それはジョナサンの父でジャズ・ヴァイオリンの名手ジョン・ブレイクやジョナサンの師でもある名ドラマーのラルフ・ピーターソンに捧げているものその理由にあるのかもしれない。緊張感や複雑さの中に不思議とリラックスしたムードが感じられるのも心地よくて、たびたび流すことになった一枚でもある。
ウォルター・スミス3世『return to casual』

ロバート・グラスパー世代のサックス奏者の最高峰ウォルター・スミス三世もブルーノートへ。テイラー・アイグスティ、マシュー・スティーヴンス、ハリシュ・ラガヴァン、ケンドリック・スコットとその世代の最強メンバーをそろえたウォルターのレギュラーバンドがすさまじい演奏を聴かせる。ブルーノート移籍っぽさはアンブローズ・アキンムシーレとジェイムズ・フランシーズがゲストで加わる豪華さかなと。
ブラッド・メルドーやカート・ローゼンウィンケル、マーク・ターナーらが00年代に作り上げてきたいわゆるコンテンポラリー・ジャズのサウンドだが、ウォルターはそれを着実にブラッシュアップし、前に進めている。複雑で繊細な作曲にも表れているし、それをいとも簡単に演奏し、そのうえでさらに個性を乗せ、曲の魅力を膨らませることができる名手たちを聴いていると、ただただため息が漏れる。
個人的に本作では近年はアルバムごとに録音メンバーを変えながらリリースしている『In Common』シリーズでも高い評価を得ているウォルターが「作編曲」の面でそのセンスを開花させているのが感じられた。2019年の『Still Casual』のころから彼の楽曲のメロディアスな魅力にひかれてきたが、『return to casual』ではその完成度が飛躍的に向上しているように感じられるのは、このアルバムの各メンバーの演奏が曲に奉仕するように奏でられていて、即興が強烈にも拘らず、それもまた作編曲の一部として聴こえること。恐ろしい完成度だと思う。
ちなみにウォルターは同時期にリリースされたケンドリック・スコット『Corridors』では、ケンドリック・スコット、ルーベン・ロジャースとのトリオでとんでもない演奏を聴かせている。今年のコンテンポラリー・ジャズではウォルターが関与した『return to casual』と『Corridors』はベストのひとつで間違いないだろう。こういった「今の時期の最高峰の成果」をブルーノートが記録していることの意味は今後、時間が経ってから多くの人が気付くのかもしれない、と僕は思っている。