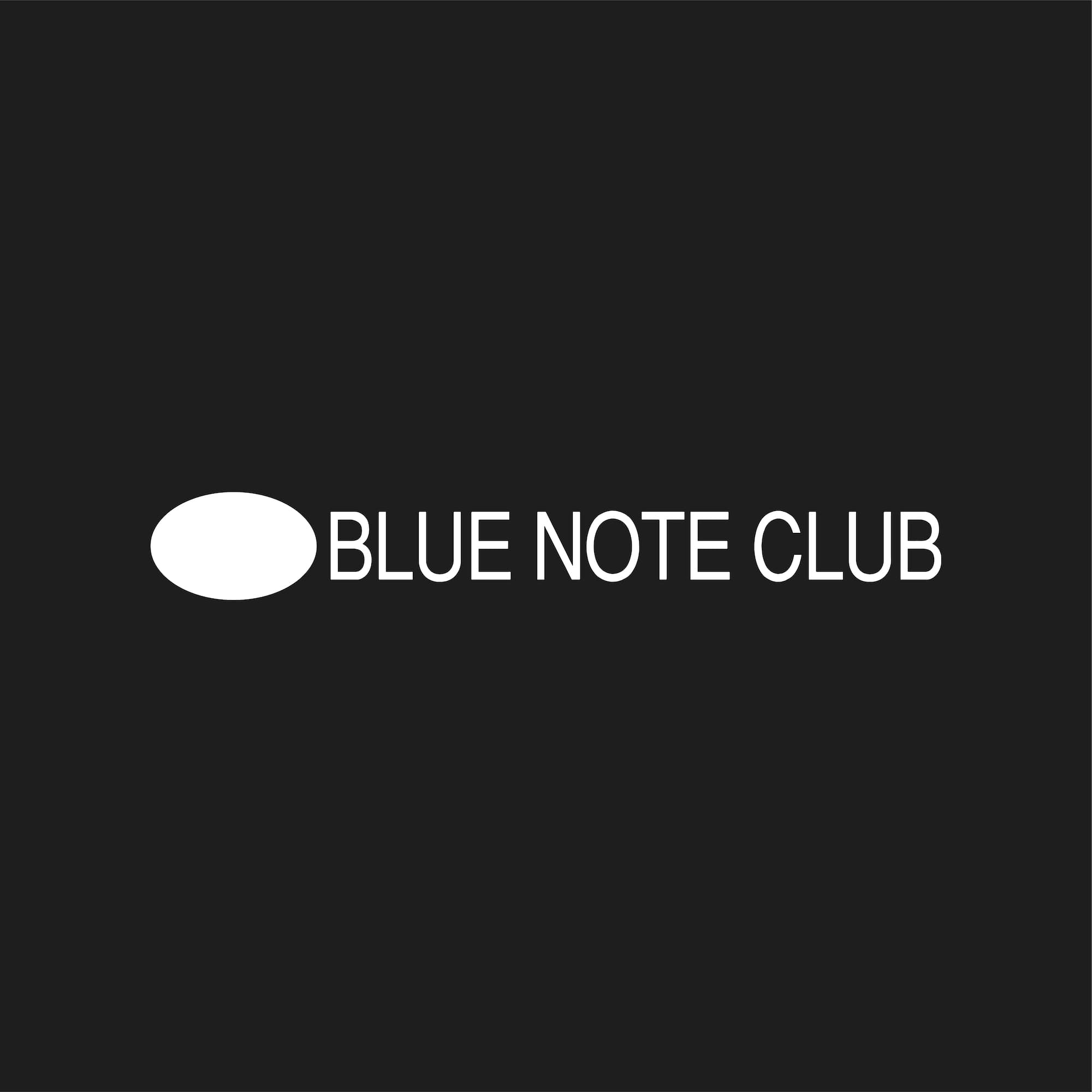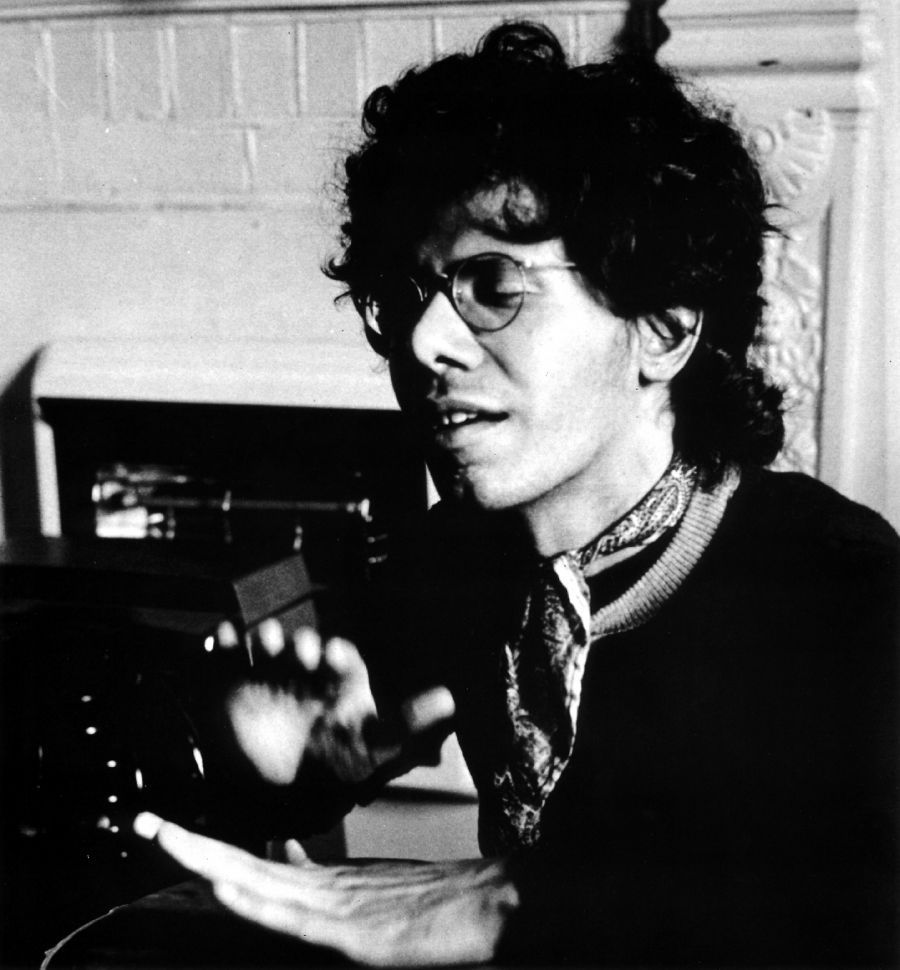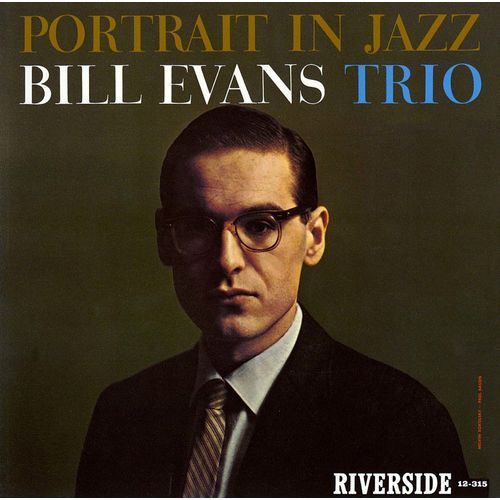英国発祥の広角型ジャズ・フェスティヴァルの日本版の第2回目が、再びゴールデン・ウィーク後の週末に行われた。場所は、秩父ミューズパーク。それは、秩父のランドマークとなる武甲山とは反対側の丘陵地に広がる、文化施設が点在する公園だ。実はここ、2004年にジミー・クリフやメデスキ、マーティン&ウッドらが出演したトゥルー・ピープルズ・セレブレイションというフェスティヴァルが開催されたことがあった。

©ito kaoru
帯状の公演内の敷地の一部に、立派な野外シアター施設を用いた<シアター・ステージ>と3方を木々に囲まれた<グリーン・ステージ>が用意される。それらは音が被らないように、交互にパフォーマーが出演する。また、<シアター・ステージ>の横にはDJテントも設置され、場に華やぎを与える。そして、会場遊歩道に沿って、飲食ブースがずらりと並ぶ。20店舗を超えていたようなそれらは、地元の食べ物やお酒(秩父には世界的に著名なモルト・ウィスキーの蒸溜所がある)を提供するお店が並んでいるのも特徴で、それを眺めるのも楽しい。お店の数、昨年よりも増えたかな。それから今年、両ステージの後の部分にドッグランのスペースが設けられていた。

©ito kaoru
以下、その2日目の模様を見た順に書いていく。午後から雨マークが天気予報では表示されていたが、降雨せず。誰もが、ゆったり。この公園にいるだけで、都市部とは異なる“緑のヴァイブ”を受けていると感じられるのも本当にうれしい。
<シアター・ステージ>の最初のアクトはPenthouse with 馬場智章。ジャジーさやソウルネスをうまく用いる現代ポップ・グループで、男女のツイン・ヴォーカルがフロントに立つ。さらにコーラスのシンガーも2人いて、アバウトに書くならもう少しポップなモノンクルといった所感を得た。そこに映画『BLUE GIANT』の主人公である宮本大のテナー・サックス音を担当した馬場がブロウをいい感じで入れる。鍵盤担当者の角野準斗はグランド・ピアノのみを弾いていたが、その音もちゃんと聞こえた。PA音、いいんだな。一部、ピアノとシンガーだけでショウを進めたりとか、ヴァリエイションにも気を使っていた。

©岸田哲平
次は、<グリーン・ステージ>。そこには先ほども勇姿を見せた、馬場智章のリーダー・グループが出演する。類家心平に続く若手トランペッターの実力者である佐瀬悠輔との2管編成のもと、エレクトリック・ジャズ傾向にある表現を堂々と展開。映画『BLUE GIANT』の演奏経験を経て、熟考した演奏から離れた勢いに任せた吹き方もするようになったと取材時に語っていた馬場だが、今回はまさにそうした姿勢の誉を彼は出していた。とともに、一方ではermhoiのヴォーカルをフィーチャーし、親しみやすさを出したりもして抜かりない。

©中河原理英
続く<シアター・ステージ>には、ブルーノートが送り出したビート創出担当のナマリ・クワテンとギター/キーボード担当のデヴィッド・ムラクポルからなるUKやんちゃ2人組であるブルー・ラブ・ビーツが登場。日本人奏者をゲストに入れた昨年末の初来日公演もそうだったが、今回もトランペッターの黒田卓也やテナー・サックス奏者の西口明宏、シンガーの鈴木真海子やARIWA(ASOUND)、Penthouseの角野準斗を曲によっては呼び込み、活劇的なビート・ミュージックをフランクに送り出す。出自は違っていても、“ジャズ+”の何かがあればカジュアルに重なることができるということを、面々は笑顔とともに語っていた。

©岸田哲平
<グリーン・ステージ>に出たBREIMENは、一瞥して引き込まれた。リード・ヴォーカルも取るベーシストが中心となる5人組だが、ファンクの酔狂をきっちり知りつつ、ミクスチャーなビート・ミュージックを作っていて、その様には高揚。いい意味での阿呆さを持ちつつ〜ドラマーはフィッシュボーンのように横向きに座っていた〜、実は一般受けしそうなメロウネスやメロディ性も抱えていて、唸ってしまう。最後のほうで、サックス奏者はソロを取ったが他のメンバー同様にやはり上手い。なんか野蛮人の仮面を被った賢人バンドという感想も持った。

©中河原理英
その後、<シアター・ステージ>に戻り見たのは、SKY-HI & BMSG POSSE (ShowMinorSavage - Aile The Shota, MANATO & SOTA from BE:FIRST / REIKO) with SOIL&“PIMP”SESSIONS。その名義にあるように、人気ラッパーのSKY-HIと彼の周辺のラッパーやシンガーの集合体に、いまや今様はみだしジャズの先駆者的存在であるSOIL&“PIMP”SESSIONSが生音サポートするという出し物だ。違和感なく、異なる世代性や音楽観が笑顔とともに重ねられる。なるほど、これはジャズ・フェスティヴァルならではの出し物と頷いた。

©岸田哲平
三度<グリーン・ステージ>に行き、Kroiを見る。先のBREIMENに感激したと思ったら、こちらにもいたく感心してしまう。Kroiもファンクをはじめ多様な音楽を鷲掴みにする意志を持つバンドだが、その濃密さやそこから浮かび上がる歌心はちょっとしたもの。ネオ・ソウルっぽい感覚も彼ら流に巧みに出すし、最後の方にはクール&ザ・ギャングの「ジャングル・ブギー」のフックをうまく引用した曲も披露してアガる。イエーイ。

©中河原理英
Kroiのショウの裏に<DJテント>で回していたのは、昨年出演したWONKのドラマーである荒田洸だった。Kroiのライヴが終わり<シアター・ステージ>に戻る際には、SOIL&“PIMP”SESSIONSの社長も荒田の横に立ち掛け声をあげて、客を沸かせている。彼もここで午後一でDJをしていたが、サーヴィス精神満点だなあ。いや、フェスを自ら楽しんでいると思わせる。そういう様に触れ、気持ちが弾まないはずがない。
そして、日も暮れトリとなる、米国現代ジャズ/ポスト・ソウル界の押しも押されもせぬ実力者たちが集ったディナー・パーティーが登場する。来日メンバーは昨年2日目のトリを飾ったキーボードとヴォーカルのロバート・グラスパー、鍵盤とアルト・サックスとボコーダー・ヴォイスのテラス・マーティン、テナー・サックスのキャラも最強なカマシ・ワシントン、ベースのバーニス・トラヴィス、ドラムのジャスティン・タイソン、テラス・マーティンと近い位置にいるヴォーカルのエイリン・レイ、グラスパー表現に欠かせないDJのジャヒ“サンダンス”レイクという面々だ。

©岸田哲平
ディナー・パーティーのアルバム群はR&B色を前に出す曲が印象に残ったが、ライヴにおいてはよりアーティスト間のインタープレイを重視しアドリブ部も拡大され、現代ジャズとしての要件や襞を仁王立ちさせていた。ステージの照明が暗く後方からではメンバーの表情を知ることは叶わなかったが、音のほうはそれぞれの持ち味や得意技をくっきりと受け手に差し出す。いいゾ。そして、それらが綱引きしあい、ソウルやヒップホップやロックも見渡した、スケールのデカい現代ジャズという像を結晶させる様には息を呑んだ。なんか、“この日、この時”といった特別と言いたくなるものを感じてしまったのは、ぼくだけだろうか。

©岸田哲平
いくつかの出し物がそうであったように、出演者の共演やゲスト参加が行われていたことに、フェスティヴァルたる意義を大きく感じずにはいられなかった。そうしたなんでもアリの臨機応変さ、順列組み合わせの自由もまた、ジャズが抱える美点にほかならない。ディナー・パーティーのこれでもかという現代ジャズ・アーティストとしての底力の提示が2日目最大のハイライトであったが、美味しいミュージシャンの噛み合わせをいろいろ享受できたのも、LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2023の見どころだったのは疑いがない。
2年の積み重ねを経て、そのディテイルはかなり出来上がった。広い層を見据えての今のジャズが持つ多様なポテンシャルの開示……。さて、来年はどのような出演者や設定がなされるのだろう。