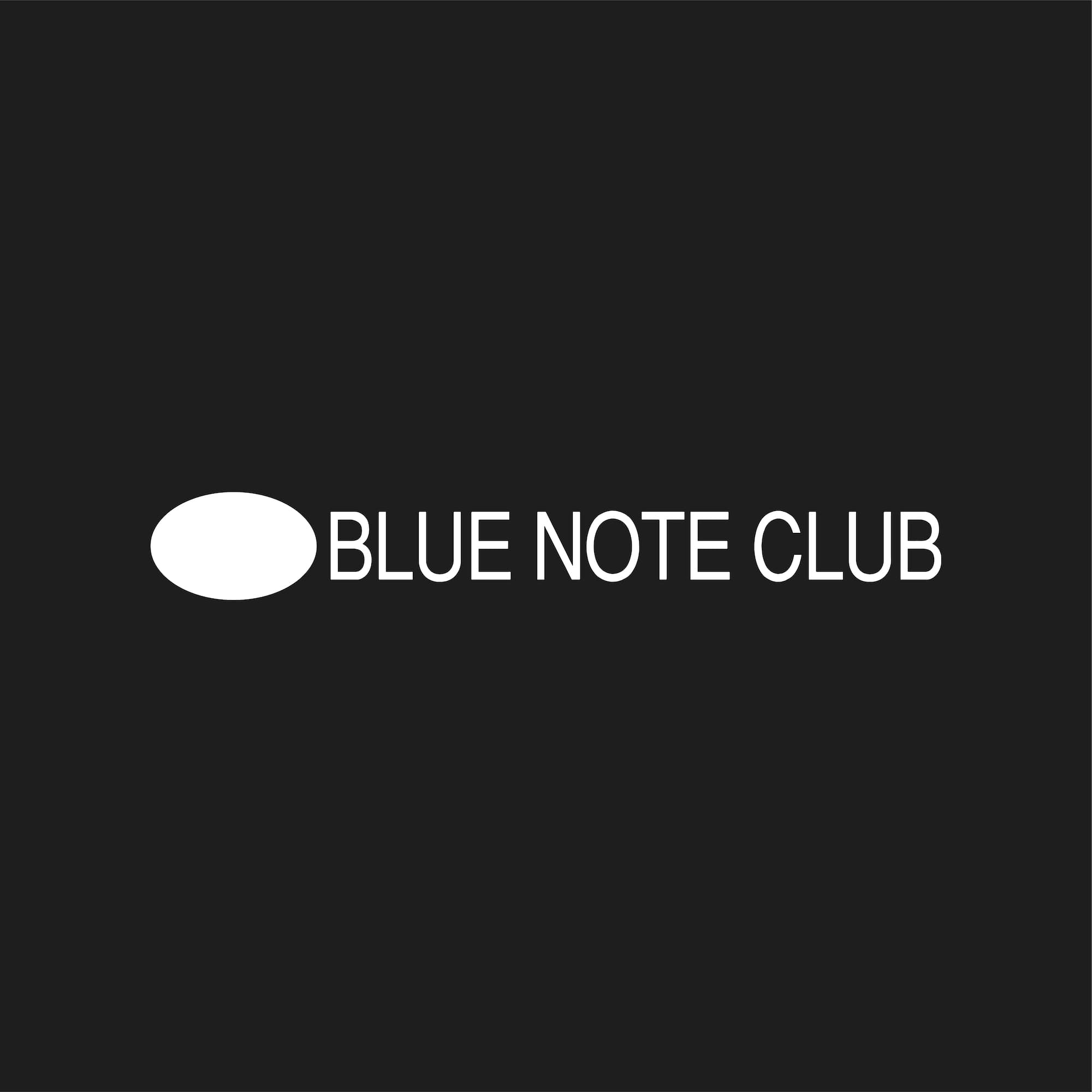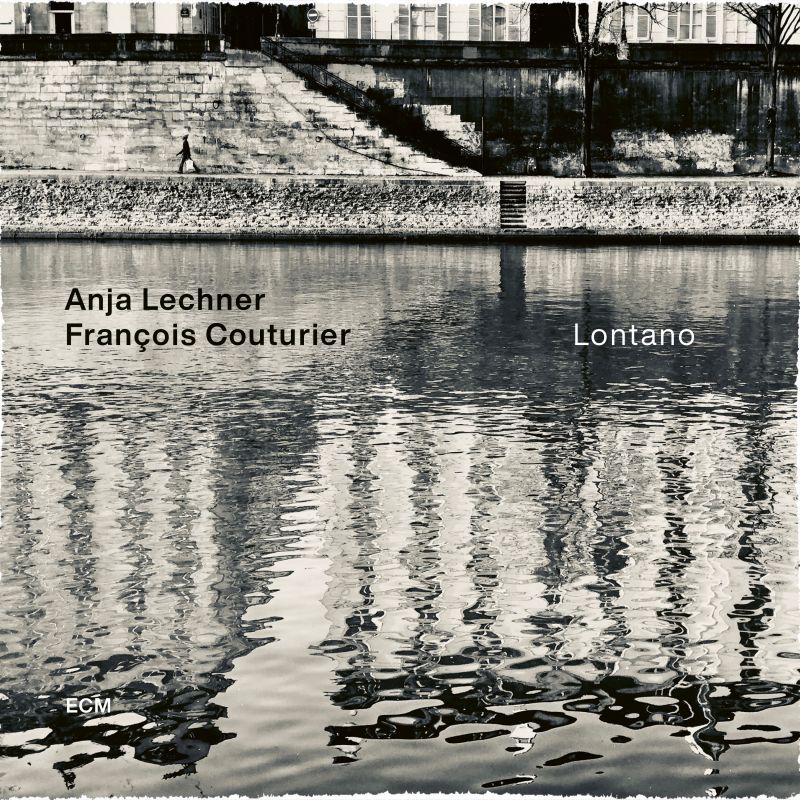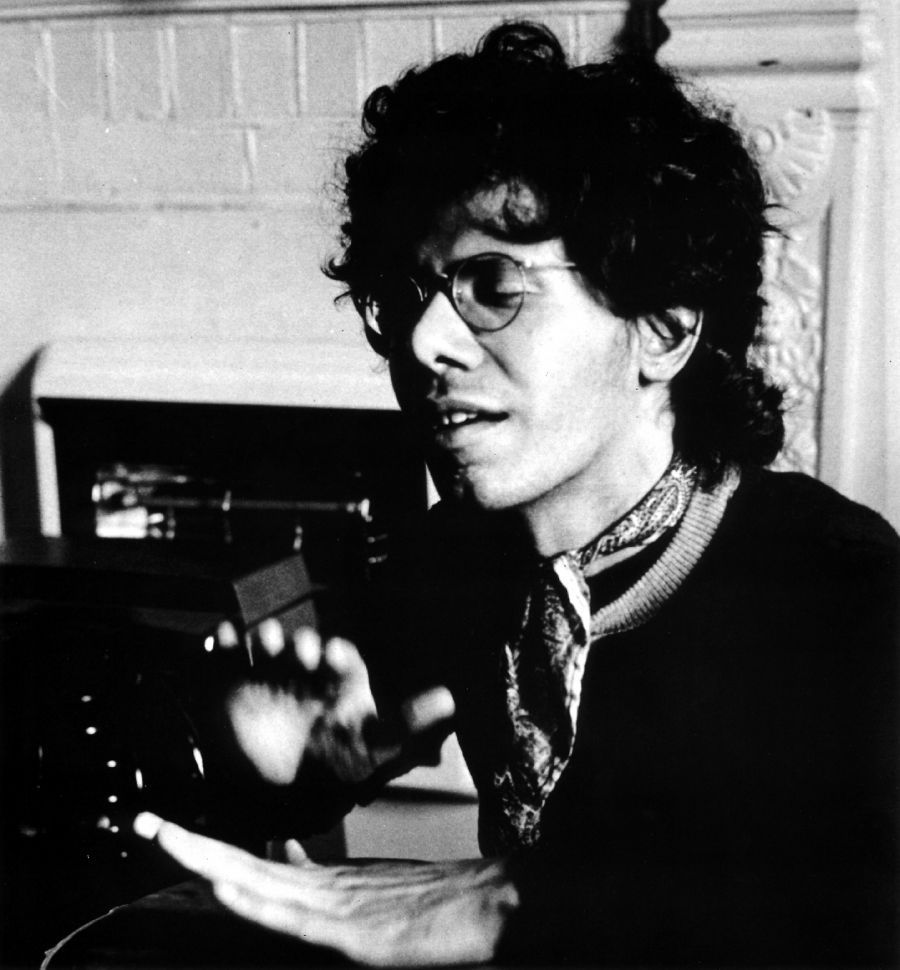第64回グラミー賞にて、最優秀グローバル・ミュージック・パフォーマンス賞を受賞し、ヴァーヴ・レコードと契約したパキスタン出身のヴォーカリスト、アルージ・アフタブ。グラミー賞にノミネートされたピアニスト、ヴィジェイ・アイヤーとベーシストのシャザード・イズマイリーとコラボレーションしたアルバム『LOVE IN EXILE』を3/24にリリースした。
この作品について、音楽評論家の佐藤英輔さんがアルージ・アフタブとヴィジェイ・アイヤーとシャザード・イズマイリーの3人にインタビュー。
そうだったんですか!
秀でたアルバムは、各々に興味深い成り立ちやストーリーを持つ。そして、在NYのパキスタン人シンガーであるアルージ・アフタブ(前作『Vulture Prince』で、グラミーの最優秀グローバル・ミュージック・パフォーマンス賞を獲得した)、ピアノ/電気ピアノ/エレクトロニクスのヴィジェイ・アイヤー、鍵盤ベース/フェンダー・ベース/エレクトロニクスのシャザード・イズマイリー、その3人連名による『Love In Exile』もまた然りだ。
実は完全即興で録音したというこのアルバムの鮮烈にして滋味に満ちた聞き味をなんと説明しようか。実はヴィジェイは現在ECMからもっとも厚遇されるピアニストだが、この『Love In Exile』も当初ECMの発売リストにあったと聞く。なるほどその流動性や響きやエキゾティシズムや今様さの存在は同社から出されてもなんら不思議はない。
結局のところアルージが所属するヴァーヴからの発表となったが、それが個を拠り所に自在に飛翔しあう同作の価値を下げるものではない。驚愕の成り立ちのもと稀有な聞き味を獲得した『Love In Exile』について、参加者3人に語ってもらった。
(2023年4月17日、日本時間9時半にzoomで収録)
Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily - To Remain/To Return
――ヴィジェイさんには2019年来日時にインタヴューさせてもらいました。シャザードさんのことは2018年のマーク・リーボウのセラミック・ドッグ公演でじっくり拝見させてもらっています。そして、アルージさんは今回正真正銘初めてです。よろしくお願いします。
アルージ「はい、あなたのエネルギッシュな感じがいいわ。さあ、始めましょう」
――アルージさんは2005年にバークリー音大に入るため米国に来て以来、その後ニューヨークに移りずっと住んでいますよね。そうさせる最大の理由はなんでしょう?
アルージ「音楽、ニューヨークというコミュニティ、すべてがあるからね」
――前作『Vulture Prince』(Verve、2021年)については、今どう感じています?
アルージ「『Vulture Prince』は構造的にも違っていたし、私のリード・プロジェクト。だから、今度の『Love In Exile』とはまったく別物よね。その次作としてこういうアルバムを作れたのはすごくクールだなと思っている。今回はメインストリームじゃない15分もあるような曲も入れたり、オープンにもうなんでもありなスタンスでやっている。そして、そんな内容に良い反応が返ってきており、私たちのリスナーってすごく成熟していると知ることができたわね」
Arooj Aftab - Mohabbat
――シャザードさんは『Vulture Prince』にも参加していましたが、今回はアルージさん、ヴェジェイさん、シャザードさん3人連名によるアルバムとなっています。そして、作編曲、プロデュースのクレジットも3人の名前が出されています。ジャケット・カヴァーも3人が並んだ写真ですし、今作はまさに3人対等のアルバムと捉えていいんですよね。
ヴィジェイ「うん、まったくその通りだ。三人が同等に貢献している」
アルージ「3人の民主的なアルバムよね」
――今回、どういう経緯でこの3人対等なアルバムを作ろうとなったのでしょう?
アルージ「これはヴィジェイのもとから始まったものなので、ヴィジェイがそのストーリーを答えた方がいいわね」
ヴィジェイ「5年前にザ・キッチンというニューヨークのヴェニューで、僕がキュレイトを任されてミュージシャンを集めたことがあったんだ。そこで僕が好きな人や信頼できる人を集め、いろんな組み合わせでステージに上がった。もちろんすでに一緒にやっている仲間もそのなかにはいたし、一方では新しい組み合わせもあったんだ。そして、この3人はその際に初めて演奏したんだけど、そのときのフィーリングがものすごくよくて、さらに続けたいという気持ちが僕には芽生えた。だから、これは本当に偶発的、自然発生的に始まったトリオだ。この3人でやったときに、とにかくこれしかないという感覚があり、またこの3人でやってみたいと思わせるものがあって、それは本当に言葉を超えた特別なものだった」

©Ebru Yildiz
――レコーディングは、まさに即興的になされたと聞いています。楽曲も決めずに3人で音を出し歌っていったということなんでしょうか。
シャザード「これをどういうふうに説明したらいいんだろうって考えていたんだけど、こういう言い方はどうだろう? スポンテイニアスだけれどもストラクチャーのあるクリエイション、という言い方を僕はしたい。3人全員が同じ構成、その骨組にまとわりつくクモの巣みたいなものを見ている。そして、それを受けて一緒に新たなものを組み上げていく。3人がマジに絡み合いながら作っているということにおいて、これはインプロヴァイゼイションという言葉に非常に近いんだけれど、でもなんか違うんだよなあ……」
――もともと、曲の骨組みたいなものはすでにあったんですか? それとも、それもなしでスタジオに入ったのでしょうか。
アルージ「私は魚の群れにたとえて話したことがあったように記憶がある。私たち3人が何かをやる、そして連鎖して次にまた何かをやりあう……そういう流れのようなものがちゃんとあって、それに際してもっとも必要とされるのがハイパーリスニング、とにかくお互いの音を聞くということ。そして、ここにスペースがあるから私がここに入ればいいかなということを繰り返していくうちに、大きな道筋が見えていく。だから、最初から曲の骨組があった訳ではない。音を出し合っていると、構成がおのずと見えてくるということね。誰かが弾いているものが、次の誰かの何かを導き出すみたいな感じで成り立っている」
ヴィジェイ「ライヴ・コンポジションっていう言い方したいな。ちょっとエレガントでいいんじゃないかな」
Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily - Shadow Forces
――今の話を聞いて、本当に特別な何かを持ち合える3人であると思わせられますし、本当に生きたレコーディングが商品化されたことが分かります。
シャザード「まったくそのとおり。日本にそういうのがあるか分からないけど、インプロヴァイズド・コメディというのがあるんだ。コメディアンがステージ上で最初の表現者として何かを言い出す。たとえば、それがどうしてゾウが逆さまになっているの、という発言だとして、それにみんながあーだこーだと絡んでいき20分くらい話が進んだところで、その伏線が回収されていくんだ。そういう流れにまかせて進んでいくコメディがあるんだけど、どうしてそれが可能かというと、やっぱり相手の話をすごくちゃんと聞いているからなんだ。また、ものすごく深い、そこに至るまでのその人の人生のなかで培ってきたヴォキャブラリーがあるからできることでもある。それと、僕たちがやっていることは共通性があると思う」
――なるほど。その一方、今作を聞いて、かように即興的にやっているにもかかわらず、ポップ・ミュージック的と称してしまうと言い過ぎですが、起承転結もぼくは曲に感じることができました。そして、それこそは、この3人だからこそなんだと思います。
シャザード「僕はまさに2日前にやったショウで、同じような感動やサプライズを味わったんだよね。この3人だからできる美があると思った」
アルージ「ポップって言ってもらえるのは、すごくうれしい。時にはヘヴィ・メタル的な音も鳴っているし、ポップなところも確かにある。それは意図したことではないけれども、さっきのシャザードの話にあったような、もう何10年も音楽修練を積む私たちが今に至るまでに培ってきた深い知識とかヴォキャブラリーみたいなものが、それを可能にさせるんだろうと思う。そして、いわゆるフリー・ジャムというだけではない、オープンさや会話の楽しさみたいなものがあるんじゃないかしら。この3人はそれぞれにコンポーザーでもあるので出来上がるものは始まりがあって中間があって終わりがあるというような、物語を抱えたものになるのね。最初に出たアイディアがただのアイディアで終わるのではなく、それが優れた曲になってほしいと思うところが私たちにはあり、結果的に稀有な表現が出位上がっていると思う。同じような考えで音楽をやっている人はいるものの、それをライヴの場で同じように表現できる仲間がいるというのは本当に大変なこと。もしかしたら私自身は今の時代の最高のミュージシャンではないのかもしれないけど、経験豊かな2人とやったなら私もいけるのよというところに来ていると思うわ」
Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily - Sajni
――歌詞は用意されたものがあったのですか。パキスタンで使われるウルドゥー語で歌ってるようなんですけど、なぜ英語ではなくウルドゥー語なんでしょうか、また、どんな内容のことを歌ったりするんでしょうか?
アルージ「なぜウルドゥー語なのかと言うと、今ウルドゥー語の気分なの。ウルドゥー語の方が母音をうまくコントロールできるということもある。私はどちらかというとヴォーカルを、言葉を顕すものとしてではなく楽器のように使う方向で用いている。私が話せる言語は英語とウルドゥー語しかないけど、ウルドゥー語の方が楽器としての歌を歌いやすいの。そして、詩の内容についてだけど、曲によりいろいろね。テーマ的としては別れとか、人を慕う気持ちとか、二人の人間が離れていく状況とか、ノスタルジアっぽいものが多い。ここで用いているのは、私がこれまで書いた既存の詩なの。それをもとに2人の音に反応して使えるものを臨機応変に選び、音に合わせて歌詞のトーンを変えていったりしているわ」
――ヴィジェイさんがヒップホッパーのマイク・ラッドと連名でリリースした『In What Language?』(Pi Recordings ,2003年)がすごい好きなんですよ。そしてこの『Love In Exile』を聞いて、もっと肉声と一緒にやるレコードを作って欲しいなと思いました。
ヴィジェイ「うん、あれは本当に特別なアルバムだったよね。やはり特別な関係性があり、本当にオーガニックのコラボレーションができたと思う。マイクは今パリ在住なんだけどエレクトロニクスにもものすごく詳しいので、彼とやることで僕はそのへんをすごく勉強させてもらったんだ。マイクはサウンドを刻み込んで、サウンドで彫刻を作っていくような音の作り方をする。それから、ヴォイスとピアノという組み合わせは、お互いの音が波紋を広げあい、影響し合っていくような特別な組み合わせだと思う。そこから生まれたものを、僕はスポークン・リズムって言っているんだ」
Vijay Iyer, Mike Ladd - In What Language?
――もう時間が来てしまったので、ここらで締めたいと思います。あと、シャザードさんは僕のなかでは自由奔放な冒険音楽のべーシストであるとともに、あなたが関わっているベス・オートンやモーゼス・サムニー作など聞いて分かるように、エレクトロ傾向にある現代ポップのリエイターとしても注目しています。とにかく、ぼくはこの3人でもっとやって欲しいと思います。
シャザード「グレイト。とにかく、日本に行きたい!」
ヴィジェイ「このアルバムの関心が高まっていると思わせるトゥイートを日本から受けているので、ぜひ行きたい」
アルージ「日本でも関心を持たれていることに、ものすごくエキサイトしているわ!」
【リリース情報】
アルージ・アフタブ、ヴィジェイ・アイヤー&シャザード・イズマイリー
AL『LOVE IN EXILE』

2023年3月24日リリース
https://Arooj-Aftab.lnk.to/LoveInExile
1. To Remain/To Return
2. Haseen Thi
3. Shadow Forces
4. Sajni
5. Eyes of the Endless
6. Sharabi
7. To Remain/To Return (Excerpt)