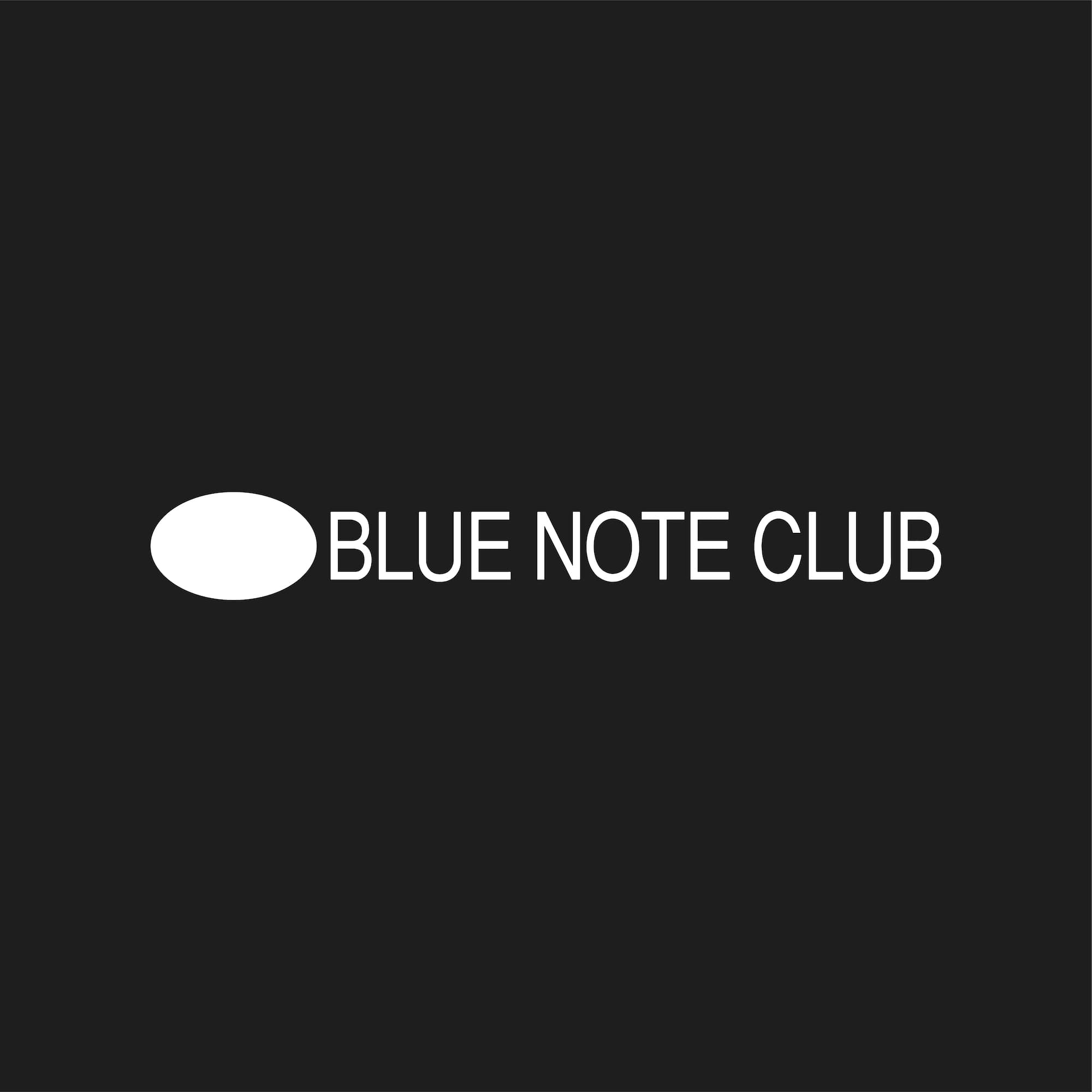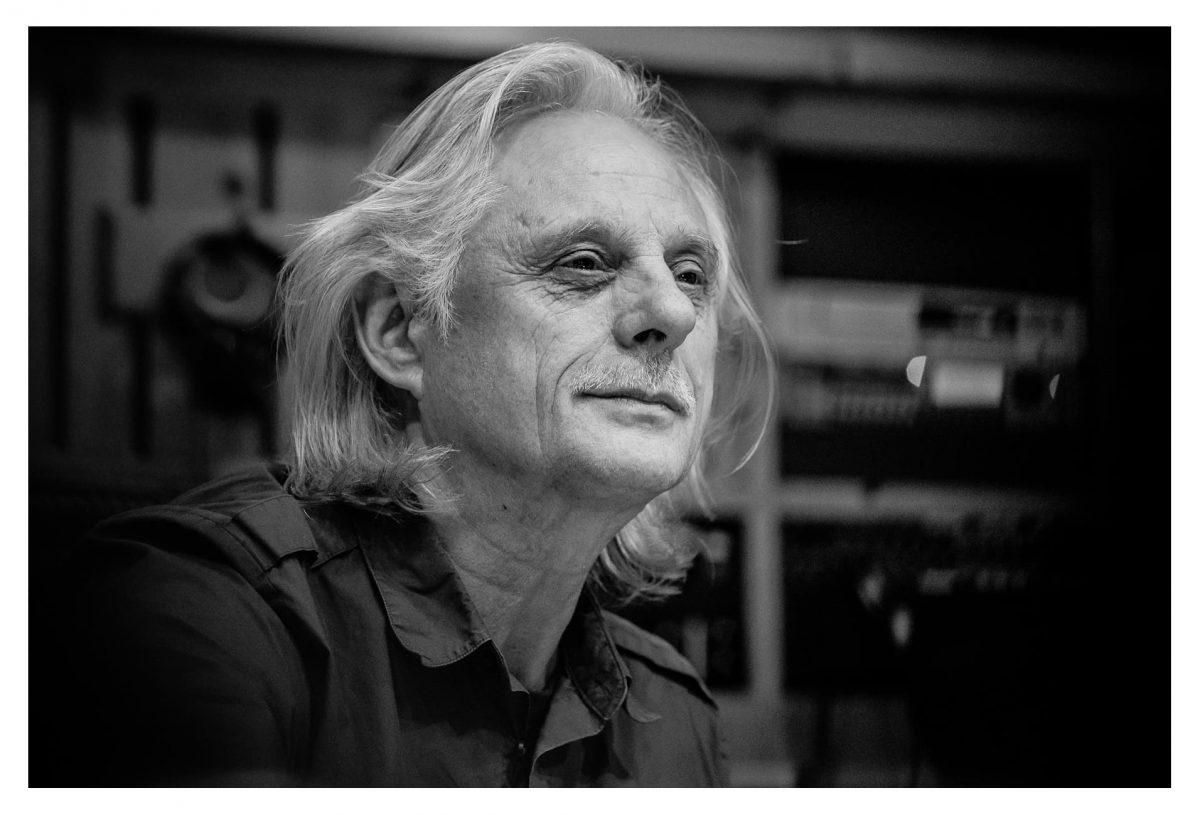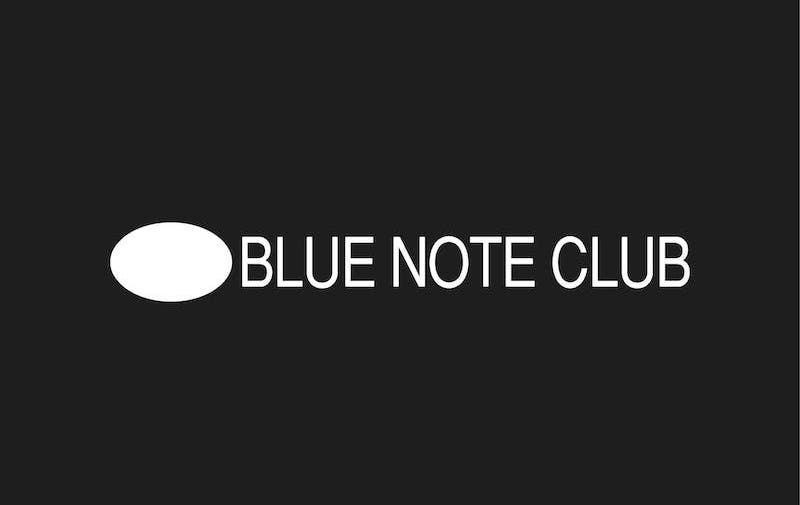2010年代末、ピアニストのジェイムス・フランシーズとヴィブラフォン奏者のジョエル・ロスの登場は大きな話題になった。彼らが20代前半の若者であったことや彼らがブルーノートからいきなりデビューしたこともその理由ではあったが、それよりもその音楽性や演奏そのものにインパクトがあった。
まず圧倒的な技術の高さには誰もが目を奪われた。そして、そのスタイルのオリジナリティは多くのリスナーを魅了した。ものすごくシンプルに言うと、彼は○○の系譜と評すことが困難な演奏をしていたからだ。ジェイムス・フランシーズのピアノにしても、ジョエル・ロスのヴィブラフォンにしてもそこには彼らの独自の演奏があるとも言えたし、同時に様々な文脈をまとめて内包しているとも言えた。何でもできるうえに、彼らにできないこともできるということだ。
そして、もうひとつのポイントは“新しさ”が語られる際に言及されがちな“越境”もしくは“混合”がその音楽の焦点になっていないことだった。“インディーロックのフィーリングを奏でることができる”もしくは“ヒップホップの感性でジャズを奏でる”など、そういった部分も併せ持ってはいたが、彼らの音楽においてはそこが前面に出ることはなかった。どちらかというと古典的な意味での“ジャズ”の枠組みの中の音楽だと認識されるようなサウンドだった。ただし、注意深く聴けば、その中には様々なジャンルの要素が潜んでいるのが作りをしていた。
それゆえにここ20年に出てきた“新しいジャズ”のようにジャズの枠を超えて需要されるような動きには至っていない。ただ、ジャズの状況を追っているリスナーたちは、これまでの20年に起きてきた大きな変化や革新に匹敵するかもしれないものが蠢き始めているのを強く感じ取っている。

少し前置きが長くなったが、ジェイムス・フランシーズやジョエル・ロスと同等の驚きを持って迎えられたのが、2020年に『Omega』でデビューしたアルト・サックス奏者イマニュエル・ウィルキンスだ。彼もまた上記の文脈で語るべき恐ろしい才能を持った新世代のひとりだ。彼らとは同世代で3人は実際に共演もしている。今のジャズ・シーンで何かが起こりつつあるとしたら、(ドラマーのジェレミー・ダットンらを加えた)このコミュニティがその現場になるのは間違いないだろう。
イマニュエル・ウィルキンスはペンシルベニア州フィラデルフィア出身。2015年からNYのジュリアード音大で音楽を学んだ。2019年にはハリシュ・ラガヴァン『Calls For Action』、 ジョエル・ロスのデビュー作『KingMaker』、ベン・ウォルフェ『Fatherhood』といきなり大きな活躍を見せる。
その間の2020年にはデビュー作『Omega』を発表。これがいきなり大きな話題を呼んで、大絶賛された。2014年にミズーリ州ファーガソンで警官により射殺された黒人青年マイケル・ブラウンと、1918年にジョージア州で起きた白人による黒人虐殺事件の犠牲者のメアリー・ターナーに捧げた曲を含むこのアルバムは、BLMにも共鳴する内容だっただけでなく、それに対する悲しみや悔しさ、恐怖、怒り、そして、鎮魂や祈りといったあらゆる情感が表現されていた。
そこで特に目を引いたのがイマニュエル・ウィルキンスのサックスだった。オーセンティックなスタイルから、90年代以降のコンテンポラリー・ジャズ、そして、ほとんどフリー・ジャズにも近い叫びや慟哭のような抽象的でノイジーな演奏まで、あらゆるスタイルを駆使しながら、様々な情感を奏でた。そこには祈りのようなゴスペルまでもが含まれていて、幅が広く、それぞれが高次元でありつつ、その上で、どれも自身の表現として昇華していて、自身の音楽と一体になっていた。それは正に“独自の演奏があるとも言えるし、同時に様々な文脈をまとめて内包しているとも言える”サックス奏者の姿だった。
それは『Omega』に参加していたピアノのマイカ・トーマス 、ベースのダリル・ジョンズ 、ドラムのクウェク・サンブリーも同様で、彼らもまたイマニュエルのような技術やセンスを有していた。だからこそ『Omega』は聴く人によっては“ただのジャズ”に過ぎなかったかもしれないが、明確に新しさが感じられた。プロデューサーとしてクレジットされているイマニュエルの師でもあるジェイソン・モランも背中を推したのだろう。
イマニュエルは2020年にはジョエル・ロスのセカンド『Who Are You?』、オリン・エヴァンス『The Intangible Between』 、2021年にはジョナサン・ブレイク『Homeward Bound』、オリン・エヴァンス『The Magic Of Now』、ジェイムス・フランシーズ『Purest Form』、急逝した名ピアニストのフランク・キンブロウのオマージュ盤『Kimbrough』に参加と、ここ2年の話題作に次々と起用されている。
ここでは、ジョナサン・ブレイク『Homeward Bound』とオリン・エヴァンス『The Magic Of Now』の2作を聞き比べるととっても彼の面白さがわかりやすく聴きとれる。オリン・エヴァンスは50年代から続くオールドスクールなジャズ寄りのワンホーンでイマニュエルのサックスは明確にフロントの立場と言える。一方、ジョナサン・ブレイクの方はこれぞコンテンポラリー・ジャズといったサウンドで複雑な構造やハイブリッドな要素がかなり入っている。コレクティブなアンサンブル側面が強いサウンドにもなっているので、イマニュエルのサックスも全体のアンサンブルのひとつといった役割が強く感じられる。それぞれでサックスの役割も演奏スタイルも異なるが、それぞれの立場で彼は個性を発揮し、作品の価値を高めることに貢献している。そのどちらでも爪痕を残せるのがイマニュエル・ウィルキンスのすごさなのかもしれない。
2022年、イマニュエル・ウィルキンスは自身の2作目『ザ・セヴンス・ハンド』を発表した。メンバーはピアノのマイカ・トーマス 、ベースのダリル・ジョンズ 、ドラムのクウェク・サンブリー、2曲でフルートのエレナ・ピンダーヒューズが加わる。プロデュースはイマニュエル自身が手掛ける。
イマニュエルのオフィシャルサイトにある情報によるとこのアルバムは7章からなる組曲になっている。『Omega』でも4章からなる組曲を収録していたので、ここでは楽曲の並びによって物語を描く方法をさらに深めている。とはいえ、アルバムの構成はかなりいびつだ。約60分の組曲の中のラスト7曲目を除いた6曲の合計時間は34分。つまり最後の7章「Lift」はなんと26分もある。この前半・後半の2部にわかれたような極端な構成がこのアルバムの面白さでもあり、重要なポイントだ。
前半の6章は実によくできていて、それぞれに全く異なるキャラクターの曲が並ぶ。「Emanation」は前半をサックスのイマニュエルが、後半をピアノのマイカ・トーマスがそれぞれ長尺のソロをひたすら弾く2部構成的な曲。「Don't Break」では、ドラムのクウェク・サンブリーの叔父のマヒリ・ファジンバ・ケイタが創設し、芸術監督も務める打楽器集団ファラフィナカン・パーカッション・アンサンブルとのコラボレーションで西アフリカに起源をもつリズムを軸にしたサウンドを展開し、打楽器だけでなくすべての楽器がリズム化し、それぞれのフレーズを反復する。
「Fugitive Ritual Selah」ではゆったりとしたテンポの讃美歌のような穏やかで優しいメロディーが印象的だし、「Shadow」ではサックスが同じフレーズを何度も繰り返しながら、その背後でピアノ・トリオが自由に動くリズム・セクションとフロントの主従逆転的な楽曲になっていたりと、それぞれの曲は構造が全く違う。
その後はフルートのエレナ・ピンダーヒューズ(クリスチャン・スコット諸作に参加していた)が参加しての2曲が続き、フルートの登場でムードが少し変化する。「Witness」ではエレナのフルートがひたすらソロを吹いていて、その背後ではイマニュエルのホーン、ピアノ、ベースも含め、まるで教会音楽のクワイヤのように音楽を重ねながらフルートの後ろで背景で反復している。
「Lighthouse」では前半はイマニュエルがひたすらソロをとり、そのバックでエレナもリズム・セクションもひたすら反復している。曲の真ん中くらいで切り替わり前述の「Shadows」のようにサックスがフレーズを繰り返し、リズム・セクションが自由に動いて、即興を繰り広げる。「Shadows」「Lighthouse」の後半に関してはマイルス・デイヴィス「Nefertiti」的コンセプトの楽曲と言ってもいいだろう。
この6曲は楽曲のテイストはそれなりに違うが、バンドの演奏の質感や全体のフィーリングが近いこともあり、6つの楽曲は自然に流れていく。僕はこのアルバムを移動中に何度も聴いていたが、あっという間に6曲が終わっていて、気付いたら「Lift」になっていたことが何度かあった。それだけ見事な展開が作り出されてる。
「Emanation」から「Don't Break」の間は曲間の無音部を無くしてメドレー的に繋がっていて、まるで2曲セットのようだし、「Fugitive Ritual Selah」と「Shadow」はその穏やかなムードで緩やかに繋がっている。「Don't Break」と「Fugitive Ritual Selah」の繋ぎも見事で、終盤でカルテットの演奏が消えて、パーカッションだけになり、リズムだけが残った状態で曲を終え、そこにピアノとベースが鳴ってゆったりと始まる流れにはストーリーを感じさせる。「Witness」から「Lighthouse」の間も曲間がなくて完全に繋がっている。
つまり、このアルバムは全体的に様々な方法で反復するリズムやフレーズとソロを組み合わせた楽曲で出来ていて、ほぼ何かしらの反復が行われている。“反復するリズムやフレーズとソロの組み合わせ”はジャズそのものと言えるし、同時にカリビアンやアフリカンの音楽にも言えることでもある。そして、それはゴスペルやソウル、ファンク、更にはヒップホップにも当てはまる。
ファラフィナカン・パーカッション・アンサンブルが参加した「Don't Break」でのアフリカ要素に耳を奪われがちだが、このアルバムではアフリカン・アメリカンの音楽が受け継いできた西アフリカ由来の要素を“反復するリズムと即興”、そして、それらがずっと繋がっていく感覚として込めているのではないかと僕は思っている。つまり、ここにはリズムパターンやフレーズなどの要素だけではなく、大きな枠組みでアフリカン・ディアスポラの文化を体現しているのではないかとも思う。
そして、彼らのようなアフリカン・アメリカンのジャズ・ミュージシャンがそういったコンセプトで音楽をやれば、そこにはジャズで言えば、エルヴィン・ジョーンズのようなアフリカ的なポリリズムやジョン・コルトレーン的な即興演奏から連なるものが含まれてくるのは納得の作りでもある。この前半の6曲だけでも、素晴らしいクオリティに驚くほかない。
そして、アルバムの最後には26分の「Lift」が収録されている。ここではフリー・ジャズと言ってもいいようなサウンドが収められている。とはいっても、現代のジャズ・ミュージシャンの語法で演奏している部分も多く、混沌というよりは、それぞれのエモーショナルな演奏がところどころで反応し合ったりするインプロビゼーションとして聴くことができる。そして、アフリカン・アメリカンだけあって、あくまでジャズの枠内の“フリー・ジャズ”的であって、決して“フリー・インプロ”にはならない。
以前、僕はイマニュエルの前作『Omega』に対して、以下のようなことを書いたことがある。
「ジョエル・ロスの音楽が抽象的な部分もかなり含みながらもどこか滑らかで洗練されたまとまりがあるのに対して、イマニュエルのジャズはかなり尖っていて、めちゃくちゃエモーショナル。ジョエル・ロスと同じコミュニティにいるのがわかるような作曲されたコンセプトのある楽曲を演奏しているし、その中で繊細に反応し合っているコレクティブな音楽でもある。ただ、その中で演奏者が自由になる時間やスペースがあり、そこではシステムやルールよりも、その楽曲が求める感情や質感やムードが重視されていて、時にはフリー・ジャズを思わせるように思いっきり抽象的に演奏することもある。ただ、それが必然であるのがわかるのと、それがそれまでの展開から自然に発生し、それに合わせてバンドの演奏も変化し、激情的な演奏さえもナチュラルに楽曲の一部として機能し、ストーリーの一部として流れるように進行していくのが面白い。明らかにアウトしたり、ノイジーだったりして、それが迫ってくることが当然のことにように思える構成がある。」
イマニュエルが出て来た時に僕はそのフリー・ジャズ的な要素に驚いたのだが、同時にそれに必然性をも感じていた。それはブラック・ライヴス・マター(以下、BLM)の時代に呼応した表現として受け取っていたからだ。アフリカン・アメリカンのジャズ・ミュージシャンたちが怒りや悲しみ、絶望や希望など、言葉にできない強く深い感情を表現するためにノイジーな音色やアブストラクトなフレーズなどを使ったのではないかと僕は思っている。
例えば、現代のジャズ・シーンで最大級の影響力があるトランペット奏者のアンブローズ・アキンムシーレの作品を追うと見えてくるものがある。2010年代前半にはダークで重いサウンドの中にBLMなどのテーマを込めていたアンブローズが2018年の『Origami Harvest』では全編でラッパー/ヴォーカリストを起用し、そのメッセージを言葉に託し、より直接的に表現していた。しかし、『Omega』と同年の2020年にリリースした『On the Tender Spot of Every Calloused Moment』ではアブストラクトでフリーキーなサウンドを自らのトランペットで奏でるようになった。声にならない声もしくは嗚咽のようなものをトランペットから吐き出す息で表現する様は言葉以上に説得力があった。
僕は『On the Tender Spot of Every Calloused Moment』と『Omega』が同じころにリリースされたことには意味があると思っている。そして、その延長に『ザ・セヴンス・ハンド』収録の「Lift」があると考えている。「Lift」は前作からさらに踏み込んだ彼らのステイトメントと言っていいだろう。様々な形での反復が織り込まれた巧みな作編曲の前半6曲の34分と鮮やかに対比させるように鮮烈に“自由”を奏でた「Lift」の26分を並べた構成の美しさとパワフルさこそがこのアルバムの素晴らしさでもある。最後に「Lift」が炸裂するインパクトこそが重要なのだ。
ちなみに『On the Tender Spot of Every Calloused Moment』では西アフリカのブードゥー由来のヨルバ語のチャントが収められていて、このアルバムでは明確にアフリカン・ディアスポラがコンセプトとして含まれている。他にもブルースやゴスペル、偉大なジャズ・ミュージシャンへのオマージュが含まれ、アフリカン・アメリカンの歴史や遺産へのまなざしもある。『On the Tender Spot of Every Calloused Moment』と『ザ・セヴンス・ハンド』には確実に同時代のアフリカン・アメリカンのジャズ・ミュージシャンに共通する意志が入っている作品だと思う。
それは若き日のイマニュエルがアンブローズに師事していたこと、もしくはアフリカン・アメリカンの偉大な遺産としての“ジャズ”をアフリカやカリブまで遡って総括しようとしているウィントン・マルサリスにもイマニュエルが師事していたことなども関係しているのかもしれない。
更に言えば、アメリカではクリスチャン・スコット、イギリスではUKカリビアンのシャバカ・ハッチングス、ブラジルではアフロ・ブラジレイロのアマロ・フレイタスらがやっている音楽の中にあるアフリカン・ディアスポラの音楽への探求とも通じているものなのだろう。シャバカもアマロもフリー・ジャズへの言及を行っていること、それと同時にミニマルな反復にもこだわりを持っていることが共存している人たちでもある。
『ザ・セヴンス・ハンド』がフリー・ジャズへの回帰ではなく、現在の流れやムードにいかに即したものなのかはそういった世界のジャズを見ていても伺えることを最後に付け加えておきたい。
■リリース情報
イマニュエル・ウィルキンス AL『The 7th Hand』
2022年1月28日発売
https://immanuelwilkins.lnk.to/The7thHand
収録曲目:
1. Emanation
2. Don't Break
3. Fugitive Ritual, Selah
4. Shadow
5. Witness
6. Lighthouse
7. Lift
■イマニュエル・ウィルキンス各種リンク
本国公式サイト: http://www.immanuelwilkins.com/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057783111859
Instagram: https://www.instagram.com/immanuel.wilkins/
Twitter: https://twitter.com/wilkinsimmanuel