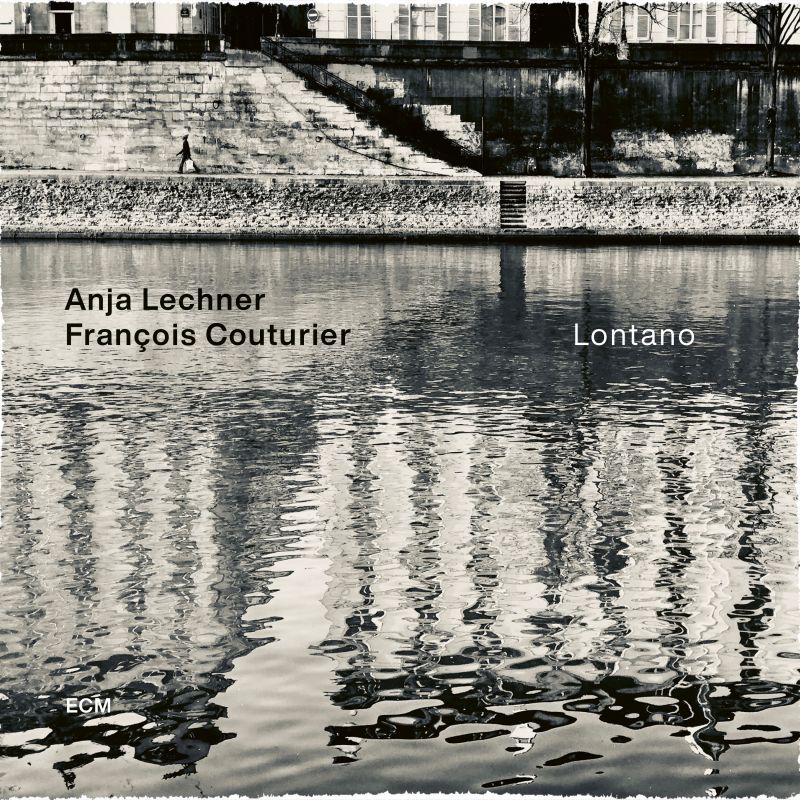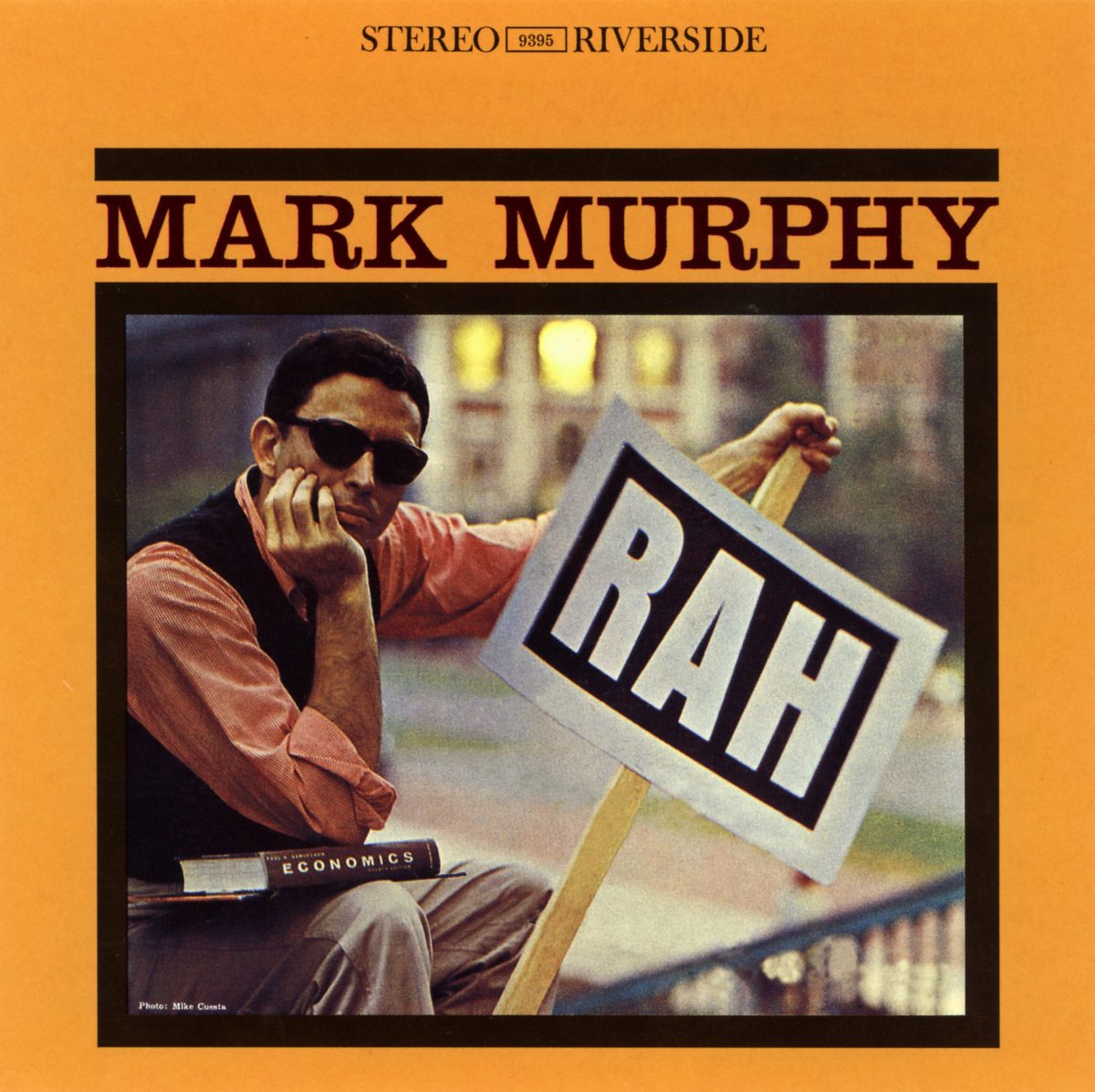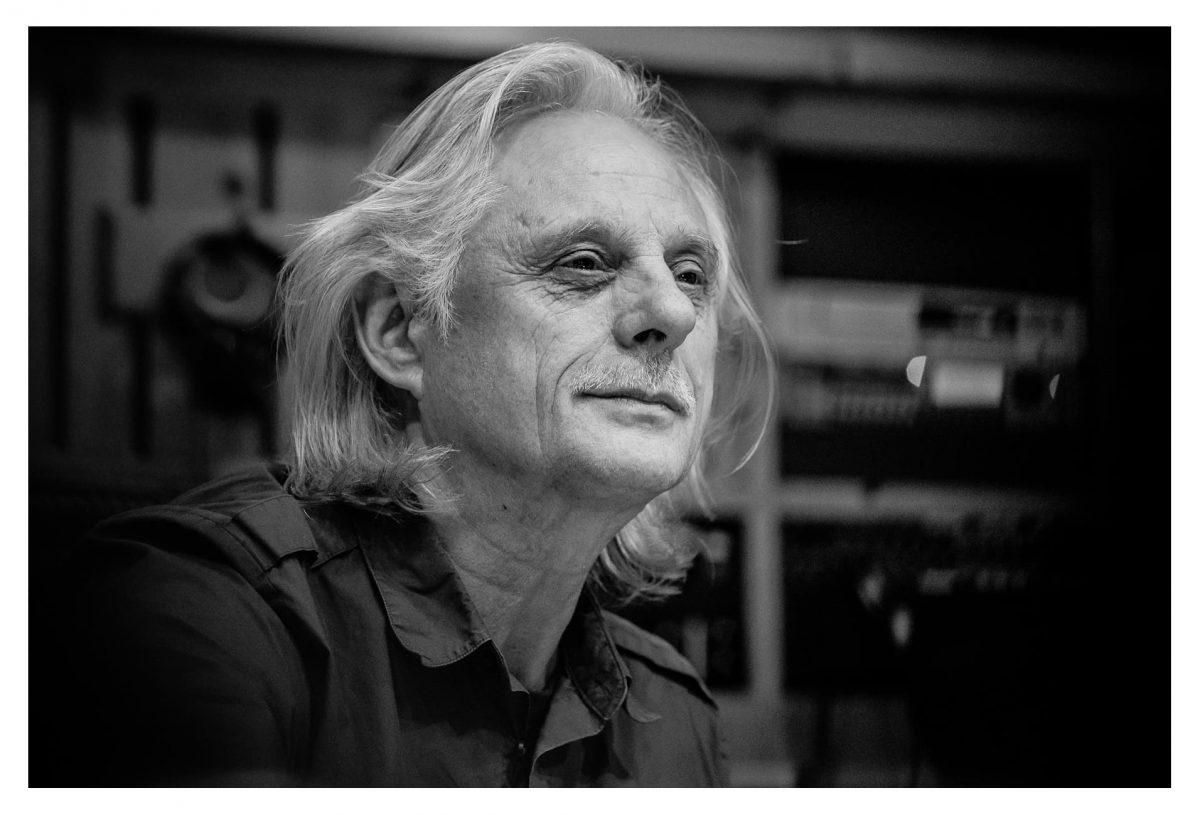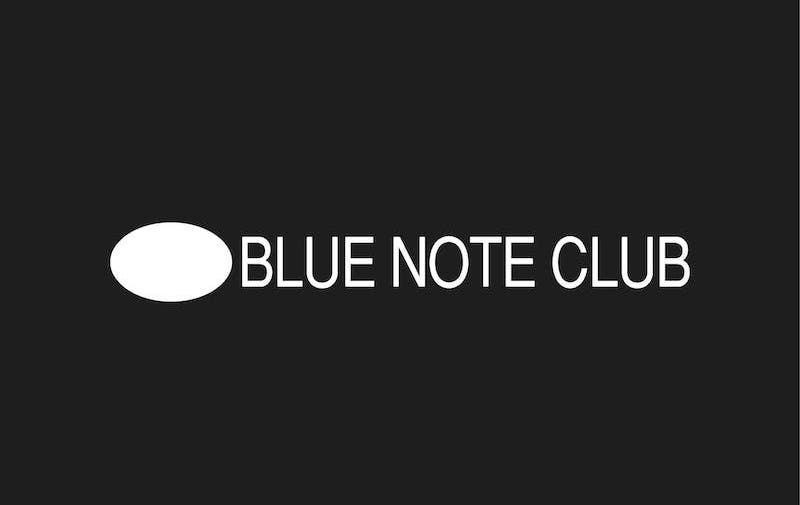(インタビュー・文)柳樂光隆(Jazz The New Chapter)
僕はサックス奏者のオデッド・ツールにずっと関心を持っていた。インド音楽にどっぷりハマり、インドにまで学びに行ったこのイスラエル人はサックスの奏法から、音楽のコンセプトまで斬新だった。これまでに聴いたことのない質感のサックスを吹き、どんなコンセプトで出来ているのかわかるようなわからないような不思議な楽曲をやっていた。そこではイスラエルのシャイ・マエストロやギリシャのペトロス・クランパニスが活き活きと、同時に他の作品では聴かれない彼らの演奏を聴くことができた。
しばらくその消息は途絶えていたが、2020年、ECMから『Here Be Dragons』が発表された。ピアノはニタイ・ハーシュコヴィッツに変わり、ドラマーとしてジョナサン・ブレイクが加わった。そこにはこれまでにリリースしていた2作以上に彼の美学がまっすぐ伝わるサウンドが鳴っていて、オデッド・ツールの素晴らしさが凝縮されてるような素晴らしい作品だった。そして、今年2022年、同メンバーでECMからの2作目『Isabela』を発表。オデッドは彼が目指している音楽の核心にまた一歩近づいたようなサウンドを聴かせてくれた。
とりあえず、彼がどんなプレイヤーで、どんな音楽家なのかを本人に聞いておく必要があると思った。彼の音楽の核にある部分について話を聞いた。
――インド音楽にのめり込んだきっかけを聞かせてください。
インド音楽が持つ音の響きは自分にとっての“音楽の中に存在する宇宙”って感覚に近かったからだと思う。もちろんジャズも大好きだったけど、フラメンコ、ブラジル音楽も好きだったし、コチャニ・オルケスタル(Kočani orkestar)やタラフ・ドゥ・ハイドゥークス(Taraf de Haïdouks)みたいなバルカン半島のブラスバンドも好きだった。なにかその中でどれが一番好きかを選べなくて、それらの中の共通しているものを体現しているのがインド音楽だった気がする。微分音(マイクロトーン)の部分とかね。音の細かいところをひとつひとつ分析していくと、インド音楽に行きつくところもあるのかなって感じたんだよね。
――インド音楽への入り口は?
最初のきっかけはジョン・コルトレーンのバイオグラフィーを読んでいて、彼が考えていたこと、特に晩年の彼の生き方に興味を持ったことなんだ。彼がインド古典音楽に興味を持っていて、息子にラヴィ・シャンカールから取った名前を付けるくらいにのめり込んでいたから。
そこからハリプラサド・チャウラシア(Hariprasad Chaurasia)、ニクヒル・バナルジー(Nikhil Banerjee)、ズィア・モヒウッディン・ダガル(Zia Mohiuddin Dagar)を聴いたんだ。当時、たまたま僕の友達のドラマーがタブラを習っていた。彼の先生の名前はサンジェイ・シャーマ(sanjay sharma)と言って、今もイスラエルにいると思う。僕も彼のところに行って、インド音楽のスケールやラーガやコードを教えてもらうようになったんだ。そこでインド音楽がジャズとは全く違う世界だと知ったんだ。なかでも音数が少ないところが興味深くて、たったの5つくらい音だけで、一晩のコンサートをやり遂げてしまうこともある。僕はその感覚に驚いてしまったんだ。
――その後、ハリプラサド・チャウラシアに師事するためにインドに行くわけですけど、どうして彼を選んだのでしょうか?
初めて彼の演奏を聴いたのはCDだったんだけど、彼の音楽は聴いてると僕の意識がぶっ飛んでしまうような感覚があったんだ。色々調べたら一学期だけ彼がオランダのロッテルダムで教えてるってことがわかった。僕の楽器はサックスだったので、そこだったらジャズミュージシャンでありながら、彼の音楽を学べるいい環境なんじゃないかなって思って、そこに行くことにしたんだ。バーンスリー(※インドのバンブー・フルート)奏者である彼の音楽を僕の楽器であるサックスでやるってことが一番の目的だった。でも、それは簡単なことではなかったんだ。なぜならインドの音楽には音と音の隙間にたくさんの音があるから、そこをサックスでどう扱うのかがポイントだった。そもそもそれをサックスでやるのが可能なのかどうかも含めて課題は多かった。僕は彼のソロを耳で聴きながらひたすらコピーしていた。まず学生として学校に入学して、その後に本人を前にしてのオーディションの時にコピーしたソロを披露したところ気に入ってもらえて、彼に師事することができるようになったんだ。
――ハリプラサド・チャウラシアはバーンスリー奏者です。彼はサックス奏者を生徒に取ったことはあったんでしょうか。
サックスを持ってきた生徒は僕が最初だったと思う。でも、彼には関係なかったんじゃないかな。だって、彼は自分のやり方を貫けばいいからね。ただ、学ぶ側の僕が困ったってだけだよね(笑)。バーンスリーって楽器は音と音がすべてスラーで繋がっていく。指による穴の塞ぎ具合で“あぁ~~ぁあぁ~ぁ~~ぁあぁ~”って音がいくらでも切れ目なく繋がってくれる楽器。それと同じことをサックスでやろうとすると”あぁ~~/あぁ~~~/あぁ~”って音と音の間に隙間ができてしまう。構造的に音と音を隙間なく繋ぐことがなかなかできなくてね。そもそも自分がこれまで習ってきたサックスの常識の中にはないものだったから。そこは自分で考えるべき部分。つまり自分で生み出さなきゃいけない技術だった。そこが一番のチャレンジだったよね。練習しながらふと”なんか俺、バカみたいだな“って思ったりもしたんだけど(笑)。でも、自分がやりたい音楽を実現するためには、なんとかしなきゃいけない課題だったんだ。
――あなたは奏法だけではなくて、音楽的にもインド音楽を自分の音楽に取り入れていると思います。それはインド音楽のラーガという概念を中心に考えたもので、それをジャズの人たちと一緒に演奏している。あなたの言葉でラーガがどんなものなのかを説明することってできますか?
ラーガは“抽象的なサウンドの捉え方”だね。そのサウンドの個性は目で見てわかるものでも、触って感じられるものでもない。つまり人間を語る時のような個性とも違う。ラーガの個性は響きとして存在するんだ。それらの響きを神様や女神と同じように崇拝の対象のように扱う人もいる。とにかくひとつひとつが、ひとりひとりが出すものが異なる世界なので、真の巨匠であれば、ひとつの音を鳴らせば“あのラーガだ!”って感じさせることができる。それ以上になにもなくても“この人が弾くあのラーガだ”ってわかるくらい個性の強いものだね。それはスケールとも違うし、メロディとも違う存在で、スケールとメロディとの挟間にある何か。その挾間にある宇宙みたいな感じだね。それが発展してメロディにある可能性も秘めているし、それはスケールの一部だと捉えることも可能なんだけど、でも、そのどちらでもない世界観なんだよね。強いて言葉にすれば、ムードや環境ってことなのかな。演奏している側も(自身の音を)聴きながら感じているものなんだ。
――なるほど。
僕は今、言ったことはブルースにも当てはまると思うんだ。ブルースってスケールで成り立っている音楽でもないし、決まったメロディがあるわけでもない。演奏によって個性がどんどん変わっていく。やるべき人が演奏していれば“これはブルースだ!”って最初の音を聴いたら伝わってしまうよね?その考え方がジャズと自分がやろうとしてるインド音楽との橋渡しになったんだ。ラーガをブルース的な感覚として捉えればいいんだなって。僕はラーガが持つ普遍性みたいなものに気づいていったんだ。
――あなたの音楽はインド音楽から影響を受けていると資料に書いてあります。ただ、あなたの音楽を聴いてもすぐにインド音楽だとわかるようなメロディやスケールやリズムもなってないし、もちろんインドの楽器も使っていない。つまり、インド音楽にある構造や要素を用いているわけではないということです。それって“インド音楽の核にあるラーガっていう概念もしくは哲学をもとに演奏している”みたいなことなのでしょうか?
そういうことなのかもしれないね。例えて言うなら比較学(Comparative Study)みたいな考え方なのかな。比較神話学(Comparative mythology)、比較宗教学(Comparative religion)、比較言語学(Comparative linguistics)色々あるよね。そういったものと同じような比較音楽みたいな考え方なのかもしれない。例えば、外国語を勉強すると、その言語の表面的な部分だけじゃなくて、その裏側みたいな存在があるのがわかるって行くし、異なる言語をしゃべっていても、そこには共通するものがあることがしばしばあることに気づくと思う。僕はその共通するもの、つまり何が“コモン”なのかってところにとても関心がある。それに気が付くと、人類によるコミュニケーションの手段としての音楽の世界におけるサウンドに関して、一見全く別のところから来たように見えるものでも、実はそこに共通点があることが多々あることに気づく。僕はその共通点を見つけるのが好きなんだ。だから、君が言うように“構造的にこっちから持ってきたものをここに入れよう”ってことが大事なのではなくて、“(別々に見えるけど)繋がっている部分がそこにはある”ことに気づいていくことが僕にとっての音楽の一番の醍醐味なんだろうなって思う。
(作品紹介)
Oded Tzur / Isabela
https://store.universal-music.co.jp/product/4506014/